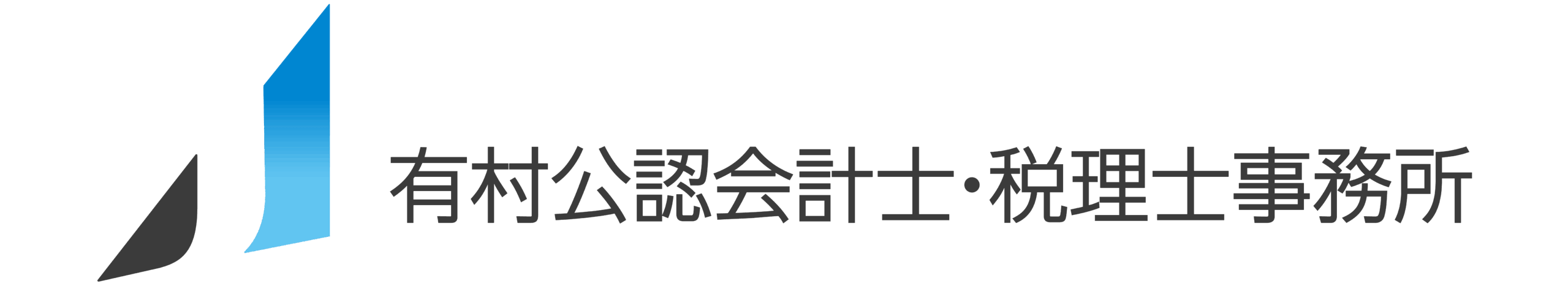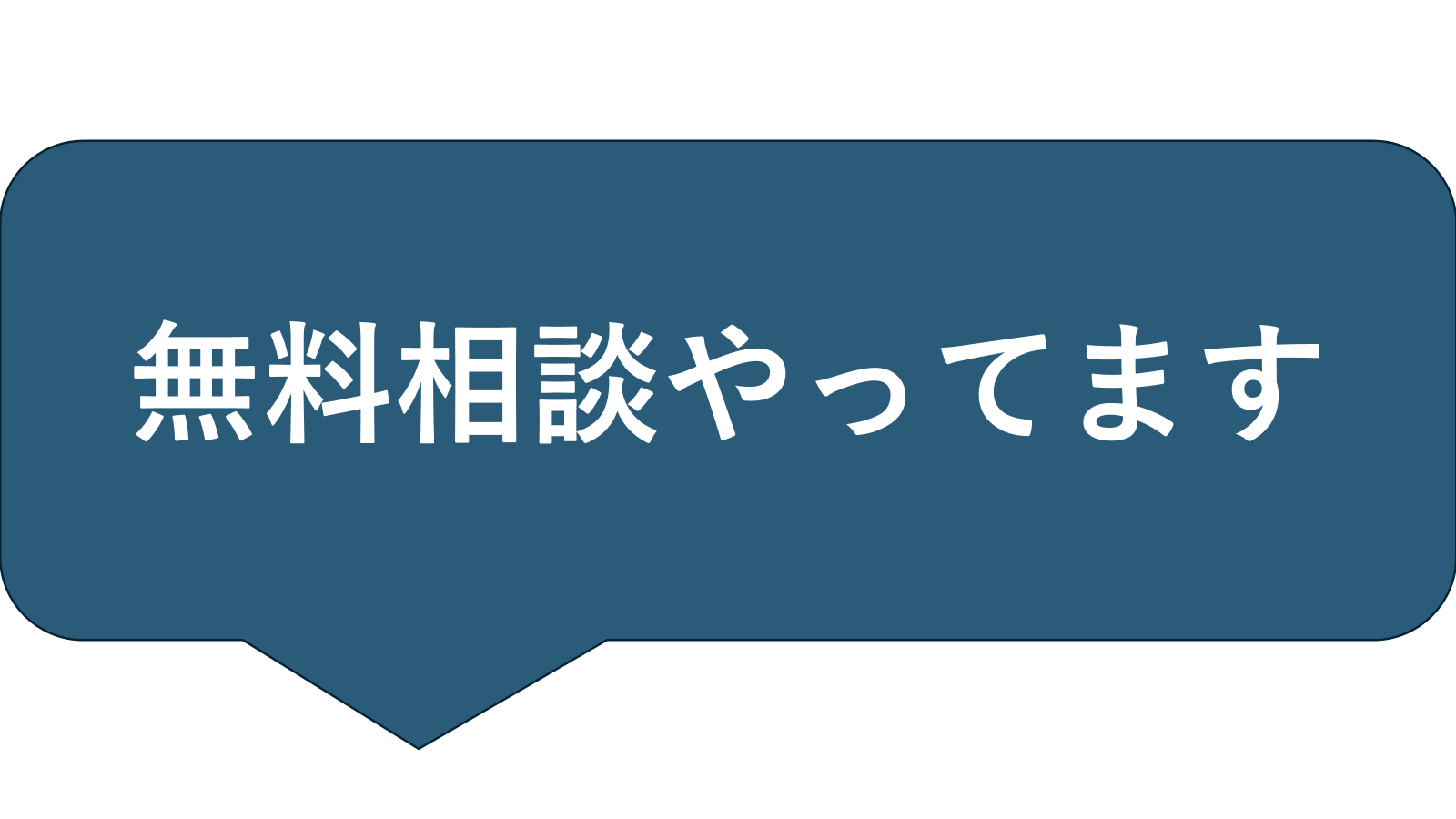固定資産(30万円未満)の減価償却方法
減価償却のおさらい
減価償却とは?いくらから対象?
減価償却とは、業務のために用いられる建物や機械装置などの資産を購入した場合に、購入した年に一度の経費とするのではなく、耐用年数と呼ばれる一定の期間にわたって少しずつ経費計上することです。取得した資産は時の経過や使用とともに価値が減少するという考え方があるためこのような経費の計上方法となっています。一方で土地は時間がたっても価値が減少せず、骨とう品のような歴史的な価値があるものも劣化するものではありませんので、こういった資産は減価償却の対象外になっています。
また、取得価額が10万円以上、耐用年数が1年以上のものが減価償却の対象となっています。
減価償却を早期で行うと節税になる
減価償却を1年など短期で行うことで経費にできる金額が増え、課税所得や利益を抑えることができるため税金の支払を少なくすることができます。基本的には定められた期間にわたって減価償却を行う必要がありますが、30万円未満の固定資産については早期に減価償却を行うことができ、これを行うことができるのが一括償却資産と少額減価償却資産です(※内容は後述)。
結局経費にできる金額自体は変わりませんが、経費に計上できるスピードが上がり、税金を支払うタイミングを遅らせることができるため、この節税対策はキャッシュアウトを伴わない課税の繰り延べに該当します(節税対策の種類と考え方についてはこちらを参照ください)。資金繰りへの影響もないため、積極的に利用するべきでしょう。
一括償却資産と少額償却資産の違い
一括減価償却資産とは
一括償却資産とは、取得価額が10万円以上20万円未満の資産について、使用した年から3年間にわたって、その年に一括償却資産に計上した資産の取得価額の合計額の3分の1を減価償却費として計上していくもののことをいいます。”一括”とあるので即時償却かと思いきや3年であることに注意しましょう。条件等は以下の通りです。
- 利用者:すべての企業及び個人事業主
- 対象:取得価額が10万円以上20万円未満の資産
- 償却方法:取得した年度から3年間で均等に償却することができます。つまり、毎年取得価額の1/3を経費として計上します
- 償却資産税:対象外
少額減価償却資産とは
少額減価償却資産とは、取得価額が10万円以上30万円未満の資産について、使用した年に取得価額の全額を減価償却費として計上していくもののことをいいます。条件等は以下の通りです。年間300万円までが利用の上限となっている点に注意しましょう。
- 利用者:青色申告をしている個人事業主と中小企業のみ
- 対象:取得価額が10万円以上30万円未満の資産
- 償却方法:取得した年度に全額を経費として計上できます(即時償却)
- 固定資産税(償却資産税): 対象 ※償却資産税は150万円までは非課税
- その他:年間300万円が上限
また、当該制度は2026年3月31日までに取得した資産が対象となっています。一方で2年ごとに期限が延期されてきているため、2026年4月以降も延期される可能性が高いと考えられています。
まとめ:30万円未満の固定資産の処理方法
さて、結局30万円未満の固定資産について結局どう処理すればよいのか見ていきましょう。
10万円未満の固定資産
全額消耗品費として計上しましょう。
10万円以上20万円未満の固定資産
一括償却資産としても3年で経費計上することも、少額減価償却資産として即時償却することもできます。
事業の状況にもよりますが、即時償却のメリットを今すぐ取りたいのであれば少額減価償却資産を優先し、償却資産税負担をなくすことを重視するのであれば一括償却資産にするとよいでしょう。
ただ、この点で悩んでも大きな差はないため、検討にあまり時間をかけずに実務上は「10万円以上20万円未満の固定資産は一括償却資産として扱う」と決めてしまうことをおススメします。
20万円以上30万円未満の固定資産
少額減価償却資産として即時償却しましょう。
消費税の取り扱い
10万円、20万円、30万円の各基準ですが、税込経理で記帳していたら税込金額で、税抜経理で記帳していたら税抜金額で判断します。