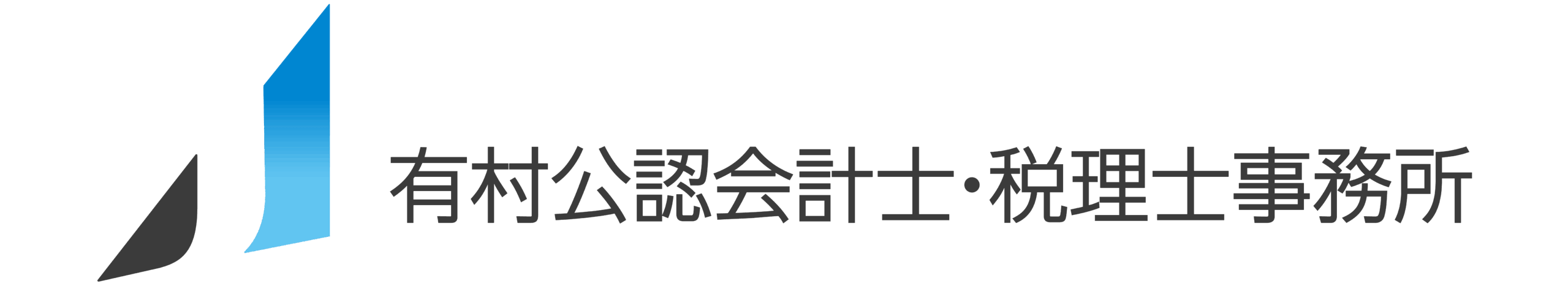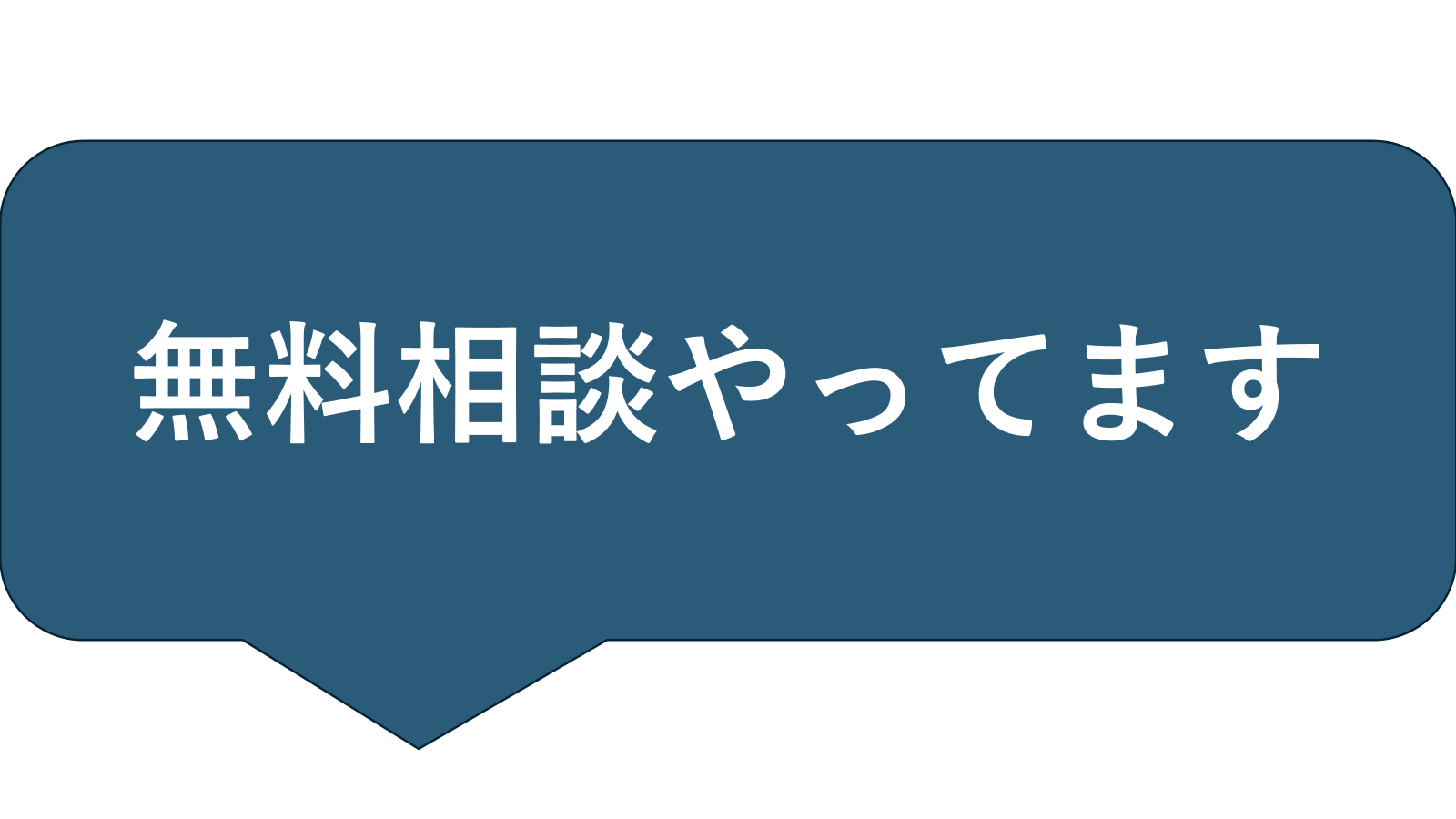小規模企業共済のおすすめ活用法
小規模企業共済の基礎知識
制度概要
小規模企業共済は、小規模企業の経営者や役員、個人事業主などのための、積み立てによる退職金制度です。 掛金は全額所得控除の対象となり、節税効果あります。所得控除とは、収入から一定の金額を差し引くことができる制度であり、税金を減らす効果があります。2022年3月時点で159万人が利用しており非常に人気の高い制度です。
利用対象
基本的に小規模企業の経営者や役員、個人事業主が対象です。その他、常時使用する従業員の数などの細かい制限もありますので詳細は中小機構のホームページで確認ください。
掛金の金額や限度等
| 掛金月額 | 1,000円~70,000円の範囲内で、500円単位で設定可能 |
| 納付方法 | 掛金の納付方法は、口座振替(共済契約者ご本人の個人名義の預金口座)。 毎月納付する「月払い」、あらかじめ届け出た月(年1回)に12か月分の掛金を納付する「年払い」、 またはあらかじめ届け出た月(年2回)に6か月分の掛金を納付する「半年払い」から選択可能。 |
| 口座振替日 | 毎月18日(土・日・祝日の場合は翌営業日) |
共済金の受取方法
共済金は、退職・廃業時に受け取り可能であり、満期や満額という概念はありません。一括または分割で受け取ることができ、一括受取りの場合は退職所得扱いに、分割受取りの場合は雑所得扱いとなります。
小規模企業共済のメリット
退職金として利用可能
事業の廃業や退職時に、それまで積み立てた金額を退職金として受け取ることができます。
なお、掛金の納付月数と給付事由ごとに、受け取れる共済金が決まっていますが、20年未満での任意解約は、掛金を下回る給付となるため注意が必要です。
「共済金A」「共済金B」「準共済金」「解約手当金」の4種類の共済金があり、退職金を受け取れる条件(=請求事由)はおおむね下記の通りです。
<個人事業主の場合>
| 共済金A | 廃業・死亡した場合 |
| 共済金B | 65歳以上で180か月以上掛金を払い込んだ場合 |
| 準共済金 | 法人成りしたため加入資格がなくなった場合 |
| 解約手当金 | 任意解約等 |
<役員の場合>
| 共済金A | 会社が解散、破産した場合 |
| 共済金B | 疾病などで役員を退任した場合 65歳以上で役員を退任した場合 死亡した場合 65歳以上で180か月以上掛金を払い込んだ場合 |
| 準共済金 | 疾病などではなく、65歳未満で役員を退任した場合 |
| 解約手当金 | 任意解約等 |
節税効果がある
小規模企業共済は掛金が全額所得控除されるため節税効果があります。所得金額ごとの節税額は以下の通りです。元の所得や掛け金の金額によって異なりますが、毎年およそ数万円~数十万円の節税効果があります。
| 課税される 所得金額 | 加入前の税金 | 加入後の節税額 | ||||
| 所得税 | 住民税 | 掛金月額 1万円 | 掛金月額 3万円 | 掛金月額 5万円 | 掛金月額 7万円 | |
| 200万円 | 104,600円 | 205,000円 | 20,700円 | 56,900円 | 93,200円 | 129,400円 |
| 400万円 | 380,300円 | 405,000円 | 36,500円 | 109,500円 | 182,500円 | 241,300円 |
| 600万円 | 788,700円 | 605,000円 | 36,500円 | 109,500円 | 182,500円 | 255,600円 |
| 800万円 | 1,229,200円 | 805,000円 | 40,100円 | 120,500円 | 200,900円 | 281,200円 |
| 1,000万円 | 1,801,000円 | 1,005,000円 | 52,400円 | 157,300円 | 262,200円 | 367,000円 |
出典:共済サポート navi より ※税額は令和6年10月の税率に基づき、所得税は復興特別所得税を含めて計算されています。
低金利での貸付利用
小規模企業共済では、事業主が資金が必要になった場合、低金利で貸付を受けることができます。 掛金の範囲内(掛金納付月数により掛金の7~9割)で、10万円以上2,000万円以内(5万円単位)で借入れをすることができる一般貸付や、特別貸付といわれる個別の事情に応じた貸付制度があります。
小規模企業共済のデメリットや注意点
掛け捨てのリスクがある
小規模企業共済は、共済金A、Bの場合には、掛金納付月数が6か月未満だと掛け捨てになります。また、準共済金及び解約手当金の場合には、掛金納付月数が12か月未満だと掛け捨てになります。掛け捨てになってしまうと一切のリターンがないということになるので注意が必要です。
元本割れのリスクがある
20年未満で任意解約をした場合、受け取れる共済金が元本割れを起こします。加入を検討する際は20年以上掛金を支払い続けられるかを慎重に判断することが重要です。
共済金を受け取るときは課税される
共済金を受け取る際は「退職所得」もしくは「雑所得」扱いになり、事業所得ではないため税負担は少ないですが、一定の課税がある点に注意が必要です。
そのため基本的にはキャッシュアウトを伴う課税の繰り延べに該当します(節税効果のタイプごとの考え方についてはこちらを参照ください)。
前納(前払い)できる
掛金を前払いすることができ、1年分の前払までは全額当期の所得から控除できます。これを利用することで最大で161万円まで所得控除することが可能です(例:1月から11月まで月7万円を支払って、12月に1年分(84 万円)を前納)。ただこちらも基本的には資金繰りに影響を与えるものであるため、慎重に検討しましょう。「前納したけどお金が足りなくなって生活が苦しい」等は本末転倒だと思います。資金繰りの影響を抑える必要がある場合は貸付制度の利用を検討しましょう。
年末の駆け込み加入についての注意点
なお、年末近く(12月など)でも駆け込み加入は間に合いますが、12月加入で前納をする場合は「現金あり」(申し込み時に現金で納付)で行う必要があります。オンラインでの申請では口座振替が前提になり、この場合は最速でも申し込みの翌々月から口座振替になるため、12月中の掛け金支払ができず、したがって当期の所得控除には間に合わないことになります。そのためオンラインでの加入申し込みではなく、金融機関等の窓口での申し込みが必要です。
おすすめの活用法
いくつかデメリットも記載しましたが、実はうまく活用すればリスクを最小化し、リターンを最大化することができます。
まず、掛金の支払いが厳しくなった場合は1,000円まで減額することができるため、財務状況が厳しい場合は減額して掛金を継続することで元本割れのリスクを最小化することができます。
また、貸付制度を積極的に利用することを強くおススメします。貸付制度を利用し、利息を支払って毎年借り換えを行えば、ずっと返済せずに繰越すことができ、実質的に資金繰りへの影響がなくなります。つまり”キャッシュアウトのない”課税の繰り延べと言えます。利息の支払いはありますが、そもそも低金利であるため節税メリットが上回ると思います。また、当該貸付制度は銀行からの借り入れなどと違い、審査がないため手続き上も非常に簡単で素早く借り入れを実行することができ、事務的な手間もほとんどありません。
貸付制度を活用する前提であれば資金繰りにほぼ影響せず、非常に有益な制度だと思いますので積極的に当制度の活用を検討するとよいでしょう。