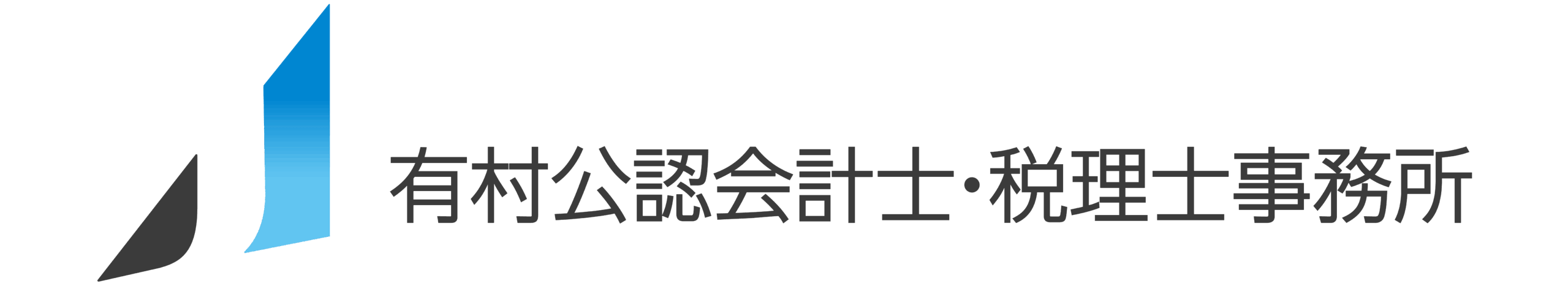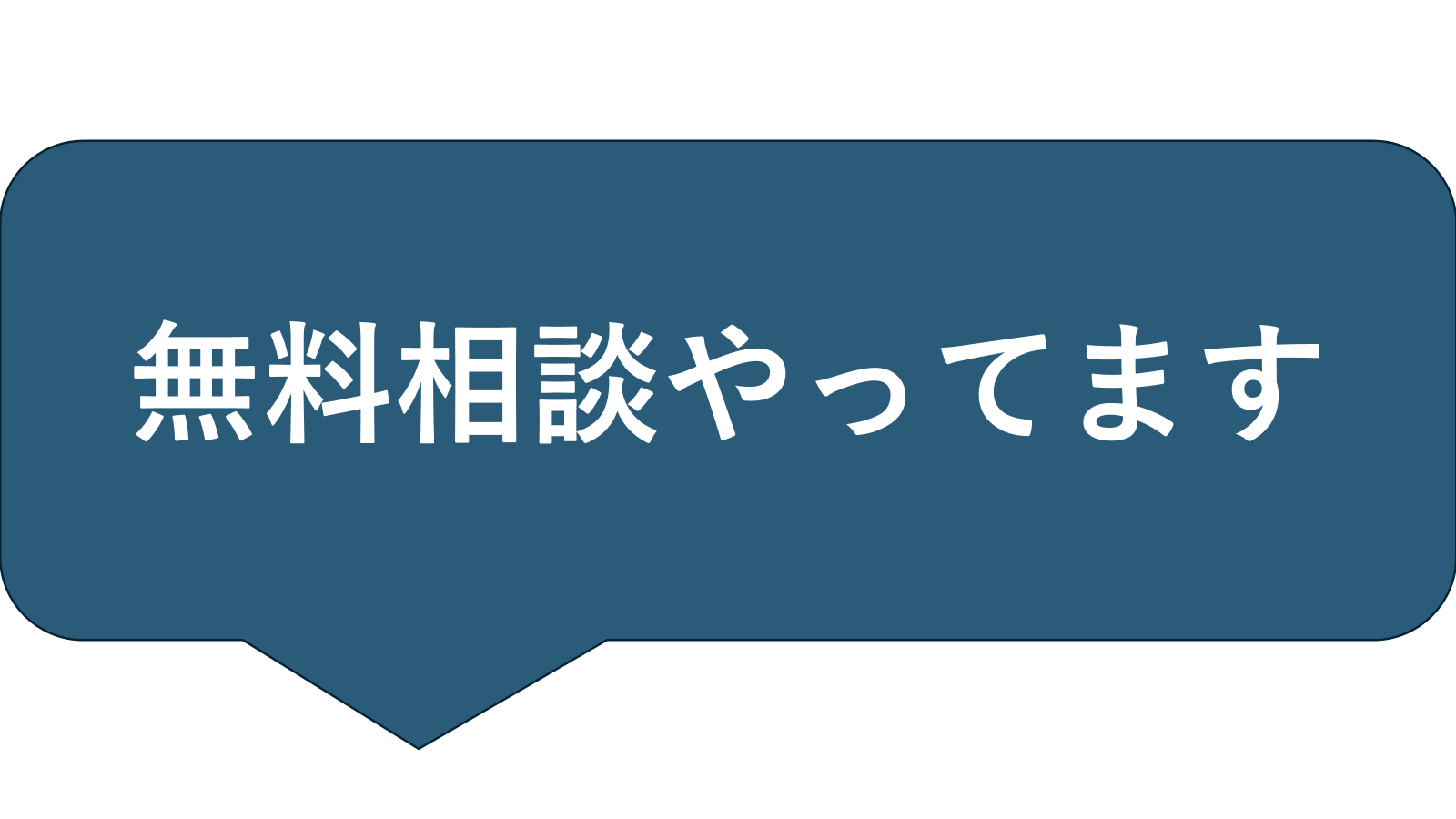による社会保険料の削減法とは?注意点も解説.webp)
役員賞与のおすすめ利用法と注意点
役員報酬の種類
経費になる役員報酬は3種類のみ
利益操作に利用されることを避けるため、役員報酬が経費として認められるためには一定のルールに乗っ取って支給される必要があります。具体的には、税法が定める「定額同額給与」「事前確定届出給与」「業績連動給与」の3種類のうちどれかに該当する必要があります。
定期同額給与:毎月同額の報酬を支払うイメージです(月50万円等)。
事前確定届出給与:役員に対する賞与のようなものですが、事前に賞与金額や支給金額を定めたうえで税務署に届け出を行う必要があります。
業績連動給与:その名の通り業績に連動した報酬ですが、適用には様々な要件があり、基本的に上場企業のみが利用できるものになります。
そのため中小企業において利用できるのは基本的に定期同額給与と事前確定届出給与のみになります。
役員賞与(事前確定届出給与)がなぜ節税手段として使われるのか
社会保険料負担を抑えることができる
役員賞与が節税手法として広く使われるのは、毎月の役員報酬(定期同額給与)の代わりに役員賞与を多く支給することで、社会保険料の金額を抑えることができるからです。社会保険料もいわば税金のようなものなので節税手段の一つとして扱われています。
下記が毎月の役員報酬と一時の役員報酬の保険料率の違いです。役員賞与における上限のほうが低いことがわかると思います。上限を超える金額については社会保険料がかからないことになるため役員賞与が利用されることになります。
<定期同額給与と事前確定届出給与の保険料率の違い>※東京都で39歳以下の場合(2024年4月納付分~)
| 定期同額給与 (毎月定額の役員報酬) | 事前確定届出給与 (役員賞与) | |
| 健康保険料 | 毎月の報酬の9.98% ※給与の上限は139万円 (=年間1,668万円が上限) | 賞与の9.98% ※賞与の上限は年間573万円 |
| 厚生年金保険料 | 毎月の報酬の18.3% ※給与の上限は65万円 (=年間780万円が上限) | 賞与の18.3% ※賞与の上限は月間150万円 |
上記の健康保険料と厚生年金保険料は会社と役員とで50%ずつ負担なので、例えば健康保険料の9.98%は会社が4.99%、役員が4.99%ずつ負担するということになります。
具体的な事例
非常に極端な例ですが、年間役員報酬1,200万円を次の2つのケースで支給する場合の社会保険料負担を比較します。
ケース①:定期同額給与100万円×12か月で支給
ケース②:役員賞与として1,200万円を支給
| ケース① | ケース② | 差額 | |
| 健康保険料 | 97,804円×12か月=1,173,648円 | 5,730,000×9.98%=571,854円 | 601,794円 |
| 厚生年金保険料 | 118,950円×12か月=1,427,400円 | 1,500,000×18.3%=274,500円 | 1,152,900円 |
| 合計金額 | 2,601,048円 | 846,354円 | 1,754,694円 |
上記の通り、役員賞与で支払ったほうが175万円ほど社会保険料を削減できることがわかります。
役員賞与(事前確定届出給与)を実施するための手続
①株主総会で支払日と金額を決定する
株主総会で支給日と支給金額を定める必要があります。株主総会で決算を確定させる必要があり、確定申告は決算日後2カ月以内(申告期限の延長を行った場合は3カ月以内)であるため、役員賞与(事前確定届出給与)を翌期に支給するつもりであればこのタイミングまでに金額と支給日を考えておく必要があります。例えば12月決算であれば2月(あるいは3月)の株主総会までというイメージです。なお、定期同額給与についてもこの株主総会で金額を決める必要がある点に留意しましょう。
②届出書を税務署に提出する
支給日と金額を決めたら以下の期限までに届出を税務署に提出する必要があります。
| 区分 | 届け出の期限 |
| 新設法人 | 設立後2か月以内 |
| 新設法人以外 | 下記のうちいずれか早い日 ① 株主総会決議日から1か月経過日 (職務執行開始日後の場合は,開始日から1月経過日) ② 会計期間開始の日から4か月経過日 |
①のかっこ書きの職務執行開始日ですが、通常は定時株主総会から次の定時株主総会までが役員の職務執行期間になりますので、株主総会の日が開始日になります。また株主総会は基本的に期末から2カ月以内(開催時期について定款の定めがあり、かつ申告期限の延長を行っている場合は3カ月以内)に行われるため、①の方が日付的に早くなります。そのため基本的には株主総会決議日から1ヶ月経過する日を期日と考えてよいでしょう。
③届け出た通りに支給を行う
届け出た通りのタイミングで届け出た通りの金額を支給する必要があります。
1日、1円でもずれると全額が経費にならないため注意しましょう。年複数回の支給を予定している場合も同様に、1回でも届け出通りに支給できないと全額が経費になりません。例えば年2回の支給で、1回目は支給日と金額を届け出た通りに支給したとしても、2回目の支給を届け出通りに行わなかった場合は、1・2回目ともに損金にできないということになります。
注意するべきポイントと活用法
役員報酬が経費として認められない場合
役員報酬が経費として認められるためには実質基準と形式基準を満たす必要があります。これらを満たしていない場合は経費にならないリスクがあります。形式基準は必ず満たしていただければと思いますが、実質基準はあいまいなものになっているため、役員賞与の金額を設定する際に根拠をしっかりと説明できるようにしておくことが大事だと思います。
形式基準は、決まった条件や手続きを守っているかどうかを判断する基準です。役員賞与で言えば下記の手続を遵守しているかどうかということになります。
- 株主総会で決議が行われていること
- 事前確定届出給与に関する届出書が所轄税務署に期限内に提出されていること
- 届出書に記載された通りの金額と時期に報酬が支給されていること
実質基準では、役員の職務内容、会社の財政状況、従業員の給与、同業類似の他社の役員給与等と比較して判断するものとされています。
おススメの支給タイミング
支給タイミングとしては決算前がおすすめです。事業が上手くいき決算前に役員賞与を払える状態であれば届け出通りに支給すればよいですが、業績や資金繰りの状況が悪い場合に支給しないという決断を行うことができ、事業状況に応じて役員賞与の支給の可否を判断することができるためです。
なお、支給しないことを決定した場合も、支給日前に下記の対応が必要です。対応しない場合は役員報酬を支給していなくても課税されてしまうため必ず対応するようにしましょう。
・取締役会等で全額不支給の決議を行う
・役員から事前確定届出分報酬の受領辞退書を受領する
支給金額の設定方法
会社の状況ごとに異なると思いますので、事業計画を策定した上で、業績に応じて支給できる役員賞与を設定すればよいと思います。
ただ、毎月の役員報酬の金額を著しく下げ、かわりに役員賞与を多額にするという極端なやり方はあまりおすすめしません。極端すぎると、先に記載した役員賞与の金額設定の根拠を合理的に説明することが難しくなるためです。その他、決算前の状況に応じて役員賞与を取り下げるという柔軟な対応ができなくなる、役員退職金の計算基礎となる報酬月額が減るため将来の役員退職金が減ってしまう等、様々なデメリットがあるため、毎月の役員報酬の金額を極端に下げることはリスクが大きいと思います。
今後の動向について
令和6年9月30日に行われた厚生労働省の第183回社会保障審議会医療保険部会の中で、毎月の社会保険料が非常に低い人がいる理由が検討されたのですが、その中で「代表取締役や役員が毎月の報酬を極端に低く設定し、高額な賞与を支給しているケースが存在する」ことが指摘されました。このため、いつ是正措置が講じられるかは未定ですが、今後は賞与にかかる社会保険料の上限額(現行は年間573万円)が引き上げられ、役員賞与を利用した節税対策の実施が困難になっていく可能性があります。