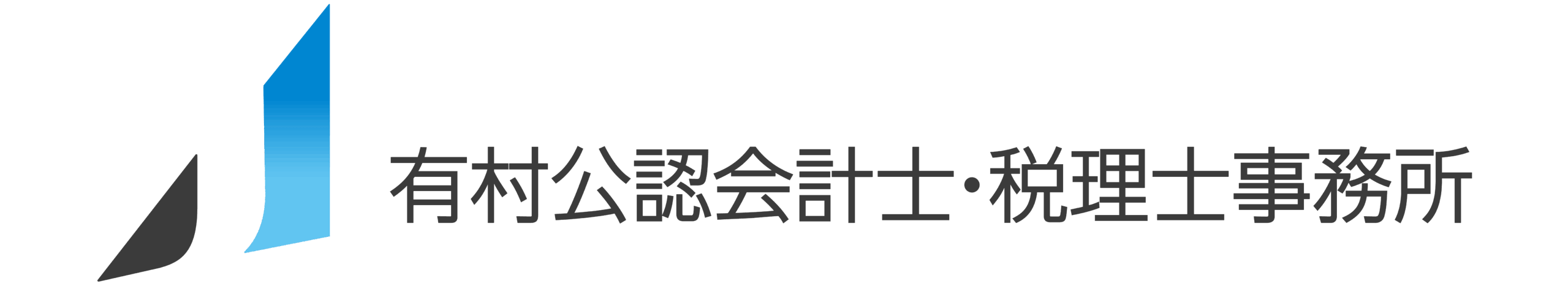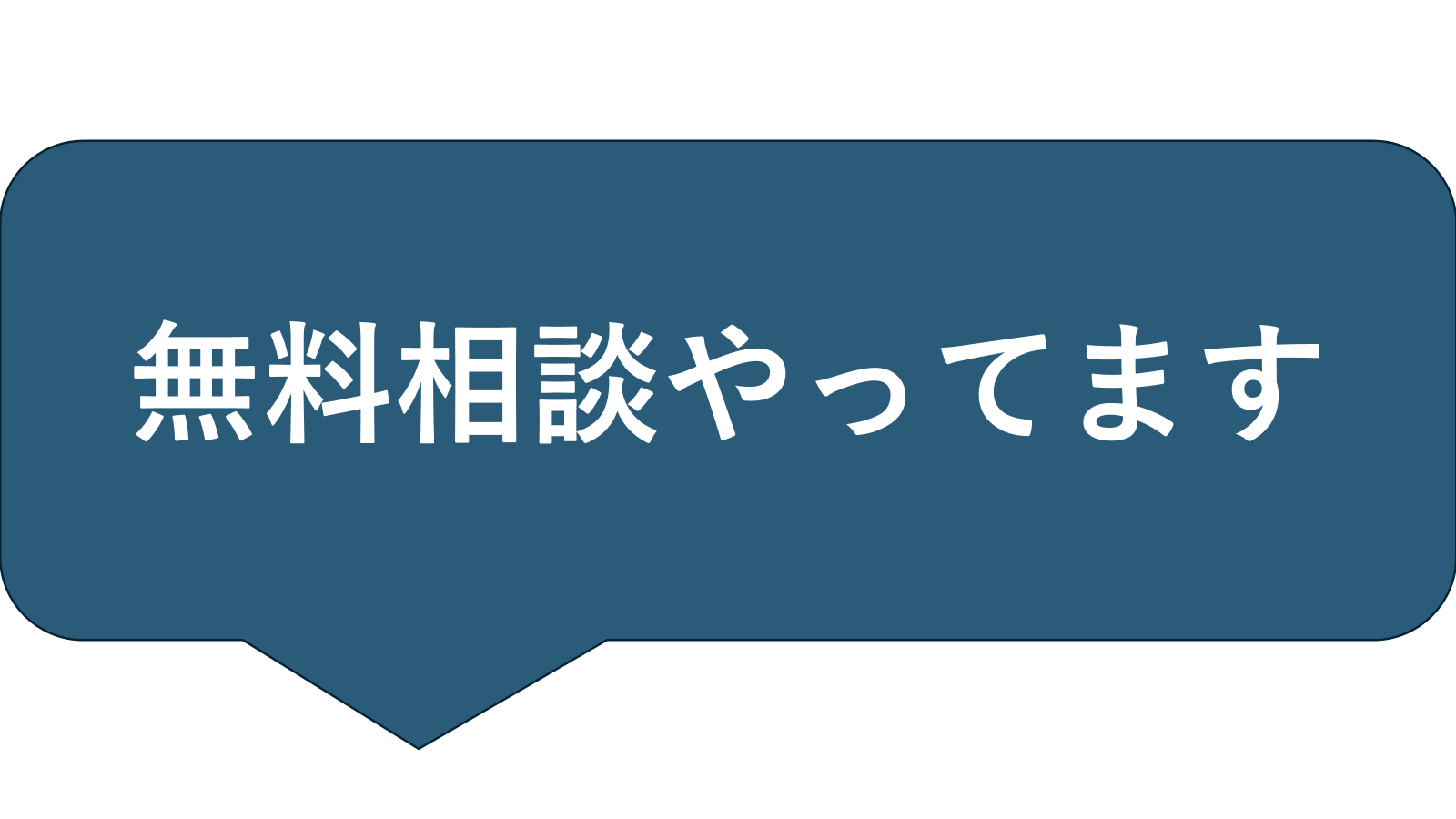社宅制度のメリット
役員や従業員に社宅を提供することは企業にとって多くのメリットをもたらす一方で、税務上の留意点も存在します。本記事では、社宅制度導入によるメリットの他、注意すべきポイントも解説します。
社宅制度の種類と導入のメリット
社宅制度の種類(社有社宅と借り上げ社宅)
①社有社宅:会社が所有する物件を従業員や役員に提供するものです。企業が直接管理し、家賃も比較的低く設定されることが多いです。ただし、企業が物件の維持管理や修繕費を負担する必要があります。
②借り上げ社宅:会社が不動産会社や個人から賃貸物件を借り上げ、それを従業員や役員に提供するものです。企業は賃貸料を支払い、従業員や役員はその一部を負担する必要があります。初期費用が少なく、柔軟に物件を選べるのが特徴です。
社有社宅は物件購入費など初期費用が非常に高く、管理コストや資産価値低下リスクなど様々なデメリットがあるため、バブル期はともかく近年ではあまり人気ではありません。そのため以下では借り上げ社宅を前提に話を進めます。
社宅制度導入による会社側のメリット
大きく2つあります。一つ目は社宅制度があることで福利厚生が充実していることをアピールできるため、採用力の強化につながります。
2つ目としてあげられるのが節税効果&社会保険料の削減です。具体的には、借り上げ社宅の家賃を会社の経費として計上し、同時に家賃負担した分について、役員報酬や給与を減額します。会社としてのトータルの費用負担額は変わらないですが、役員報酬や給与の減額に伴い対応する社会保険料を削減することができます。
社宅制度導入による役員・従業員側のメリット
役員・従業員側にも節税効果&社会保険料の削減効果があります。役員報酬や給料という形で支払いを受けてそのあとに個人で家賃を支払う形ではなく、会社が家賃を代わりに支払ってくれることになるため、仮に家賃分の役員報酬や給料が家賃対応分だけ下がったとしても、実質の手取りは変化せず、しかも所得税と社会保険料の負担をそれぞれ減らすことができる、という金銭的なメリットがあります。
節税メリットの種類
節税には①課税の繰り延べや②税金を実質的に減額させるものがありますが(詳細はこちらを参照)、全ての人々にとって家は必要であり社宅制度がなくとも自己で支払っているかと思います。これを会社の経費とすることで所得税や社会保険料を減らすことができるため、②の税金を減額するものに該当します。資金繰りにも影響しないため積極的に導入を検討すべきだと思います。
住宅手当との違い
住宅手当は給料の上乗せとして支給されるため、法人側では経費になりますが、会社と個人(役員・従業員)双方において社会保険料が発生します。個人(役員・従業員)側でも所得税が上がり社会保険料負担も発生してしまうため、社宅制度(借り上げ社宅)の方がメリットが大きいでしょう。
社宅制度導入の際の留意点
法人名義で契約する必要がある
”社宅”であるため、賃貸契約の際に会社が名義人になる必要があります。社宅制度導入の際は法人名義に変更を行うか、転居して新たに法人名義で賃貸契約を交わす必要があります。
役員や従業員から一定金額を徴収する必要がある
一定金額を会社が役員・従業員から徴収する必要があります。
下記に計算方法を記載しますが、細かく定められているため具体的な計算については税理士に確認するとよいでしょう。一定額を受け取っていない場合は社宅経費が給与として課税されてしまう可能性があるため、必ず対応するようにしましょう。
役員から徴収する家賃の計算方法
役員からは賃貸料相当額と呼ばれる金額を徴収する必要がありますが、社宅のサイズや耐用年数によって計算方法が異なります。
まず、下記に該当するものは小規模な住宅にあたります。該当しないものは小規模な住宅でない住宅となります。
- 建物の法定耐用年数が30年以下の建物 ⇒ 床面積が132平方メートル以下
- 建物の法定耐用年数が30年を超える建物 ⇒ 床面積が99平方メートル以下
①役員に貸与する社宅が小規模な住宅である場合
次の(1)から(3)までの合計額が賃貸料相当額になります。
(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2パーセント
(2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))
(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22パーセント
②役員に貸与する社宅が小規模な住宅でない場合
会社が家主に支払う家賃の50パーセントの金額と、下記で算出した賃貸料相当額とのいずれか多い金額が賃貸料相当額になります。
(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12パーセント
※ただし、法定耐用年数が30年を超える建物の場合には12パーセントではなく、10パーセントを乗じます。
(2)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6パーセント
③役員に貸与する社宅が豪華な住宅である場合
「豪華な社宅」と判断された場合は「通常払うべき家賃」が賃貸料相当額になります。
豪華な社宅とは、床面積が240平方メートルを超えるもののうち、取得価額や支払賃貸料、内装などの要素が総合的に豪華と判断されるものを言います。床面積が240平方メートルを超えていなくても、プール付きの物件など個人の嗜好を著しく反映した住宅は豪華社宅と判断される可能性もあります。
従業員から徴収する家賃の計算方法
従業員の場合には、賃貸料相当額(=次の(1)から(3)の合計額)の50パーセント以上を徴収する必要があります。
(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2パーセント
(2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))
(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22パーセント
家賃以外の費用負担の範囲についても考えておこう
会社が負担すべき合理的な理由があるものについては会社が負担しても問題ないと思いますが、そうでないものは原則個人負担とすべきでしょう。
例えば社宅の提供に伴ってどの物件でも基本的に発生するもの(仲介手数料など)は会社負担とし、それ以外(駐車場代、水道光熱費など)は個人負担とする考えが基本でよいと思います。何を会社負担し何を従業員負担とするかは社宅規程等で定めるとよいでしょう。
社宅代行サービスを利用するかどうか
従業員のいない1人会社の場合は特段不要かと思いますが、従業員が多い場合は社宅に関する手続きの管理も煩雑になります。
契約手続や送金などの事務作業の代行サービスを提供している会社もあるため、社宅制度を導入する際は代行サービスを利用するかどうかも併せて検討するとよいでしょう。
まとめ
社宅制度は会社にとっても個人(役員や従業員)にとっても金銭的なメリットが多い制度であるため、積極的に導入を検討すべきでしょう。
一方で賃貸料相当額の考え方など難しい部分もあるため、導入の際は税理士にご相談されることをお勧めいたします。当事務所でもご相談をお受けしておりますのでお手軽にお問い合わせください。