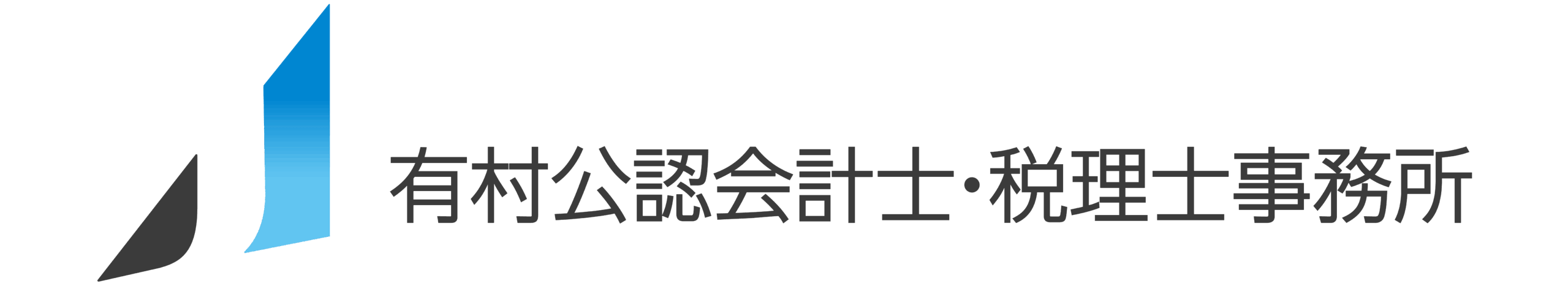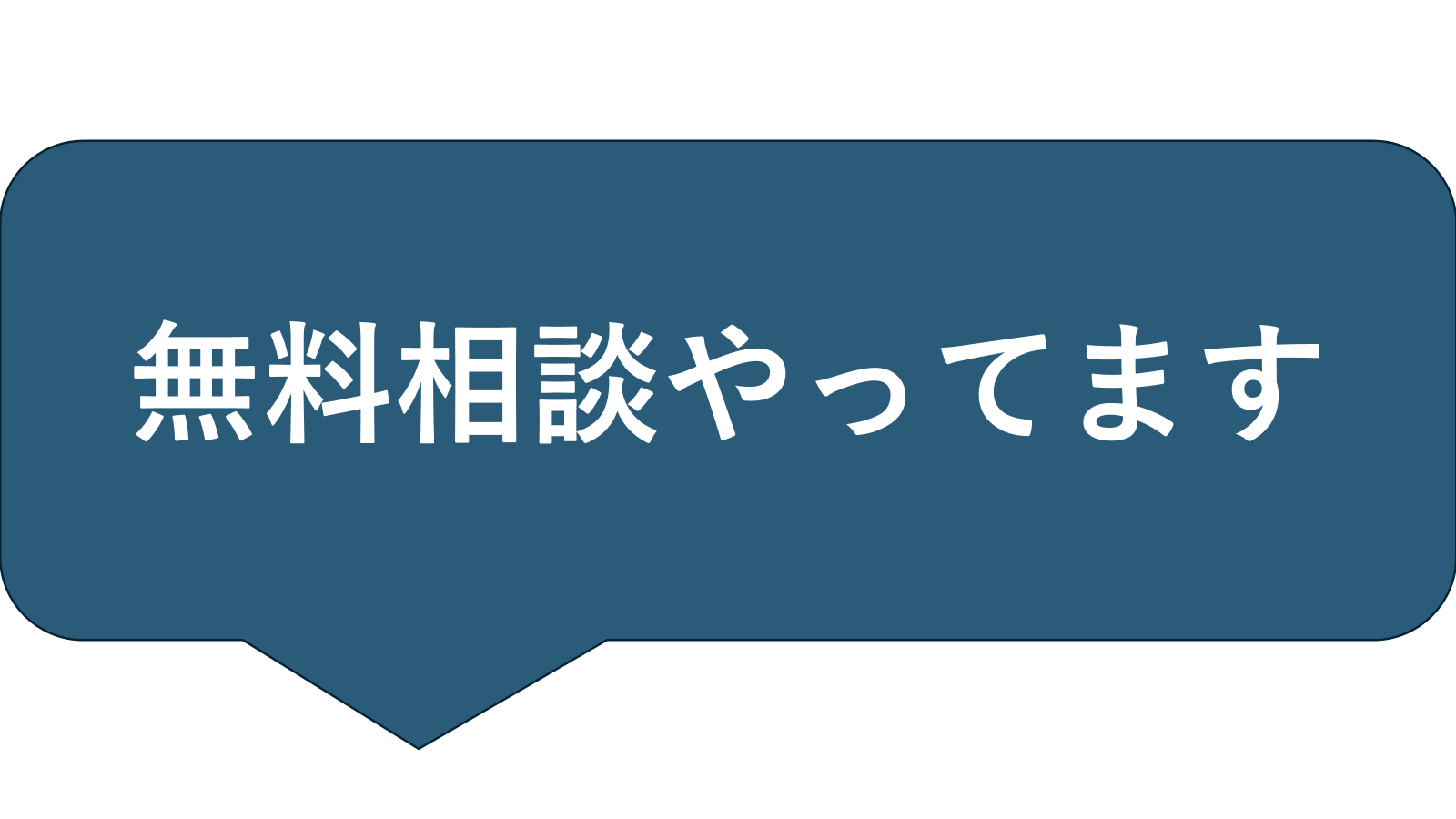日本政策金融公庫の創業融資の流れと対策
多くの方にとって起業時の資金調達は避けて通れない道であり、日本政策金融公庫の創業融資はまず検討すべき選択肢だと思います。比較的創業時でも融資を得られやすいとされていますが、審査に通るためにはしっかりと準備する必要があります。本記事では、日本政策金融公庫の創業融資の全体的な流れや審査対策等について詳しく解説します。
日本政策金融公庫における創業融資の概要&メリットデメリット
日本政策金融公庫の創業融資制度(新規開業・スタートアップ支援資金)の概要
日本政策金融公庫における創業融資制度の名称は「新規開業・スタートアップ支援資金」となっており下記が概要です。なお、金額や返済期間などの細かい融資条件は申請者の状況や融資担当者の判断によるため、最終的な着地がどうなるかについては一概には言えないことに注意が必要です。
<新規開業・スタートアップ支援資金>
| 項目 | 概要 |
| 対象者 | 新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方 ※適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方のみ |
| 資金の使い道 | 新規事業または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金 |
| 融資限度額 | 7,200万円(うち運転資金4,800万円) |
| 返済期間 | 設備資金:20年以内(うち据置期間5年以内) 運転資金:10年以内(うち据置期間5年以内) |
| 利率 | 基準利率 ※所定の要件に該当する場合は特別利率を適用 ※新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方はさらに下記の創業支援貸付利率特例制度を利用可能 ・各融資制度に定める利率-0.65% ・ただし、雇用の拡大を図る場合は、各融資制度に定める利率-0.9% ※利率の詳細は下記の出典URLでご確認ください。 |
| 担保 | 要相談 ※新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方は、原則として無担保・無保証人 |
出典:「新規開業・スタートアップ支援資金|日本政策金融公庫」を元に当事務所作成
対象者についての詳細は【日本政策金融公庫の創業融資】いつまで申請できる?創業前でも可能?タイミングの疑問を解説 の記事で記載していますのでご参照ください。
日本政策金融公庫の創業融資のメリット
①創業初期でも審査が通りやすい
銀行や信用金庫といった他の金融機関に比べて、創業時でも審査が通過しやすいです。これは、日本政策金融公庫が政府によって100%出資されており、それ自体が利益を追求する組織ではなく、「民間金融機関の補完的な立場」であることから、民間金融機関等ではなかなか融資できない方に対しても積極的に融資を検討するスタンスを持っていることが理由です。
各金融機関の特徴については融資はどこから受けるべき?金融機関の種類と選び方を解説の記事で解説していますのでご参照ください。
②民間金融機関等に比べて低金利
①と同様の理由で、日本政策金融公庫は政府系金融機関であり民間の金融機関よりも「事業者を応援していこう」というスタンスが強いため、信用力がない創業初期の融資時においては他の銀行や信用金庫よりも基本的に金利を低く設定しています。
公庫の金利の目安については【日本政策金融公庫の創業融資】金利の目安や特徴をわかりやすく解説 の記事で解説していますのでご参照ください。
創業時の融資制度としてよく比較される自治体の制度融資との差については【創業時】どっちが有利?公庫の創業融資と制度融資(東京都&品川区)を比較の記事で解説していますのでご参照ください。
③無担保・無保証
以下で詳細は記載しますが、日本政策金融公庫の創業融資制度である新規開業・スタートアップ支援資金においては、新たに事業を始める方や事業開始後税務申告を2期終えていない方については原則として無担保・無保証人となっています。一方で民間の金融機関から事業資金を借り入れる際、経営者保証という形で代表者の保証が必要になる場合があります。
担保や保証については【日本政策金融公庫の創業融資】担保・連帯保証人・経営者保証なしで利用できる?の記事で解説していますのでご参照ください。
④返済期間が長め
新規開業・スタートアップ支援資金の返済期間は、「設備資金でれば20年以内(うち据置期間5年以内)」、「運転資金であれば10年以内(うち据置期間5年以内)」となっており、長期間の返済期間を希望することが可能です。長期にすればするほど資金繰りの観点では有利ですが、一方で利子負担は重くなるので、両者のバランスを見ながら返済期間を設定することが必要です。
返済期間の詳細については【日本政策金融公庫の創業融資】返済期間&据置期間の決め方をわかりやすく解説の記事で解説していますのでご参照ください。
⑤審査機関が短く、着金までのスピードが速い
民間の金融機関からの融資の場合、創業直後で事業の実績が少ないため信用保証協会による保証を付けてから行う「保証付き融資」になることが多く、金融機関の審査だけでなく信用保証協会の審査も必要になることから日本政策金融公庫からの融資に比べて時間がかかる傾向にあります。申し込みから融資までの期間は日本政策金融公庫の場合は3週間~1カ月くらい、民間金融機関の保証付き融資の場合は1~2カ月程度が目安となっています。
保証付き融資(とプロパー融資の違い)についてはプロパー融資をわかりやすく解説!企業に最適な資金調達法とはの記事で解説していますので参照ください。
⑥個人事業主も利用しやすい
新規開業・スタートアップ支援資金は個人事業主も対象になっており、事業者が個人事業主か法人かどうか等で融資の受けやすさは変わらないため個人事業主でも問題なく利用できます。
日本政策金融公庫の創業融資のデメリット
基本的にメリットがデメリットを上回ると思いますが以下に注意です。
①固定金利のみ
新規開業・スタートアップ支援資金の利息は固定金利のみとなっており、変動金利は選択できません。そのため日本経済の動向や事業の業績に関わらず、融資実行時の金利が継続適用されることになります。
②担当者からの積極的なコミュニケーションや提案がない
創業融資のみならず日本政策金融公庫からの融資全般に言えますが、融資以降のコミュニケーションがほとんどありません。民間の金融機関の場合、営業担当者が会社に定期的に訪問したり他のサービスについての提案等を行ってくれることがありますが、日本政策金融公庫の場合はこういったコミュニケーションは期待できません。煩わしさがないため人によってはメリットともいえるでしょう。
日本政策金融公庫における融資の流れ
①事前相談
日本政策金融公庫には「事業資金相談ダイヤル」という無料の相談窓口があり、融資を申し込む前に疑問等がある場合はこちらから電話で相談することができます。必要資料に関する疑問や、融資までの流れ等について詳細に伺うことができるため活用をおススメします。
②融資の申し込み&必要書類の提出
申し込みは郵送なども可能ですが、インターネット上での手続きが便利で、日本政策金融公庫HP「事業資金 お申込受付」から行うことができます。こちらの画面でメールアドレスを登録すると登録したアドレス宛に申し込み用のURLが送付され、URLをクリックすると申込者情報や申込内容の入力画面へ進むことができます。この段階で希望する融資の金額や返済期間、資金使途等について記載することになります。
融資希望金額に関する詳細については【日本政策金融公庫の創業融資】いくら借りれる?融資金額の目安をわかりやすく解説の記事で解説していますのでご参照ください。
なお、申込画面の中で「新規開業・スタートアップ支援資金」を指定する場所がないためこのまま進めて大丈夫だろうかと不安になる方もいると思いますが、公庫の担当者が申込者の状況に応じて最も有利な融資制度で検討してくれる形になっているため、これから創業or創業間もない方であれば新規開業・スタートアップ支援資金が基本的に適用されるはずと考えてよいです。あらゆる特別利率についても、申込者にとって最も有利なもので検討されるため事前に全て把握する必要はありません。もし公庫担当者が提案する融資制度が申込者の想定と異なる場合は、面談の際に担当者に理由を質問するとよいでしょう。
情報入力が終わると同URL上で必要書類も提出することができます。主な必要書類は下記になりますが、申し込みフォーム上でも必要書類が自動で表示されるためもれなく提出するようにしましょう。
| 個人の場合 | 法人の場合 | 備考 |
| ① 最近2期分の確定申告書 | ① 最近2期分の確定申告書・決算書(勘定科目明細書を含みます。) | – |
| ② 見積書(設備資金をお申込の方) | ② 最近の試算表(決算後6ヵ月以上経過している場合または事業を始めたばかりで決算を終えていない方 | – |
| ③ 見積書(設備資金をお申込の方) | – | |
| ③ 日本公庫電子契約サービス(国民生活事業)利用申込書 | ④ 日本公庫電子契約サービス(国民生活事業)利用申込書 | ・電子契約サービスを利用の場合に必要 ・利用申込書は日本政策金融公庫のHPよりテンプレートをダウンロード可能 |
| ④送金先口座の預金通帳の写し | ⑤ 送金先口座の預金通帳の写し | |
| ⑤企業概要書または創業計画書 | ⑥ 法人の履歴事項全部証明書または登記簿謄本 | ・国民生活事業の事業資金をはじめて利用する場合に必要 ・企業概要書や創業計画書は日本政策金融公庫のHPよりテンプレートをダウンロード可能 |
| ⑥ 運転免許証(両面)、マイナンバーカード(表面のみ)またはパスポート(顔写真のページおよび現住所等の記載のあるページ) | ⑦ 企業概要書または創業計画書 | |
| ⑦ 許認可証(飲食店などの許可・届出等が必要な事業を営んでいる方) | ⑧ 代表者の運転免許証(両面)、マイナンバーカード(表面のみ)またはパスポート(顔写真のページおよび現住所等の記載のあるページ) | |
| ⑨ 許認可証(飲食店などの許可・届出等が必要な事業を営んでいる方) |
出典:日本政策金融公庫HP「ご提出書類 【インターネット申込用】」を当事務所で加工
必要書類に関する詳細については【日本政策金融公庫の創業融資】必要書類をわかりやすく解説の記事で解説していますのでご参照ください。
創業計画書の記載方法に関する詳細については【日本政策金融公庫の創業融資】事業計画書(創業計画書)の書き方を解説 の記事で解説していますのでご参照ください。
③担当者からの連絡
インターネットでの申し込みが完了してから数日すると面談日時の調整と面談時にもってきてほしい追加資料についての連絡があります。
面談時の追加資料の例としては、本人確認できる免許証、自己資金を示す資料(通帳等)や、事業所等の賃貸借契約書などがあります。追加で依頼された資料についても忘れずに準備するようにしましょう。ネットバンクを利用している際は面談当日にパソコンやスマホから口座残高や入出金明細の確認を行うことがありますので口座にログインできるようにしておきましょう。
④面談
面談時は提出した書類に基づいて担当者から質問がされますので、しっかり準備してから望むようにしましょう。面談の所要時間は30分から1時間程度です。申込者本人が面談に臨む必要があり、代理人による対応は不可です。
(参考)創業融資の面談でよく聞かれる質問事項
- 創業した動機
- 過去の経歴や関連する経験
- ビジネスモデル、商品やサービスの内容と特徴
- 市場の状況や差別化の方針
- 事業所の場所とその場所を選んだ理由
- 事業の見通し
- 人員採用の見通し
- 他からの借入状況
- 不動産等の預金以外の自己資産の状況
⑤審査
審査の期間は一般的に1~2週間程度で、提出した書類や面談内容に基づいて行われます。担当者から追加で質問がくる場合もあるため、きちんと回答するようにしましょう。
⑥融資の決定通知&契約
審査が終わると結果について電話か郵送かのどちらかで通知が行われます。申し込み時に電子契約サービスの利用申込書を提出した場合は所定のURLが送られてくるためそこから電子契約手続を行い、同時に印鑑証明書等の追加書類の送付を行うことで契約手続きが完了します。書面の場合は収入印紙が必要になるため一定の費用が発生します。
⑦振込み
契約締結後は公庫から融資金額が申し込みの際に指定した口座に入金されることになります。タイミングとしては日本政策金融公庫が契約書類を受領してからおおむね3~4営業日後程度です。
審査対策のポイント
他の金融機関でも同様ですが、融資審査に落ちてしまうと一定期間(※半年等と言われることが多い)は申し込みができないため、必ず対策をするようにしましょう。特に①~③が重要です。
①自分の信用情報を確認する
大学の奨学金の返済が滞っていたり、公共料金の支払いが遅れていたり、未納の税金があったりすると、「この人に融資してもきちんと返済してくれない可能性が高い」と判断されてしまうため、審査上不利に働きます。過去に重大な返済トラブル等が確認された場合は一発アウトで審査落ちとなることもあります。申し込み者の信用情報については公庫も必ずチェックするため、こういった情報に不安がある人は下記の会社で自身の信用情報を開示請求して対応するようにしましょう。
| 信用情報機関 | 保有する情報 |
| 株式会社シー・アイ・シー(CIC) | クレジットカードやスマートフォンの端末代金の分割払いに関する情報等 |
| 日本信用情報機構(JICC) | 消費者金融の利用履歴等 |
| 全国銀行個人信用情報センター | 奨学金や住宅ローン等の銀行ローンに関する情報等 |
支払い期限を1日でも超えた場合は「延滞」と判断され、61日以上超えた場合はより重い「異動」という記録が信用情報として残ります。
開示請求した結果、「異動」情報が載っている場合はいわゆる「ブラックリスト」扱いになるため融資が非常に厳しくなります。「延滞」を1,2回程度であれば審査上マイナス評価ですが融資を否定するものではないため申し込みに進んでも問題ありませんが、過去に金融トラブルを起こして「異動」情報が載っている場合は情報が消えるまで申込を控えた方がよいでしょう。信用情報機関ごとに異なりますが、滞納を解消してから5年間が信用情報の保存期間の目安です。
経営者の信用情報は融資判断の基礎となり最も重要な部分であるため、滞納をしないように日頃から注意を払いましょう。
信用情報についてはブラックリストの場合は創業融資を受けられる?信用情報の確認方法や対策について解説 の記事で解説していますので参照ください。
②十分な自己資金を用意する
融資の条件として明示されているわけではないですが、公庫が行っている融資先の創業企業を対象として実施した調査(「新規開業実態調査」)の記載では、必要資金に占める自己資金の割合が概ね毎年平均25%前後となっているため、自己資金の割合は2割から3割程度を目線とすべきでしょう。「堅実に事業のためにお金をためれる人」という印象を与えるため、より多い方が審査上プラスです。
自己資金の必要性については【日本政策金融公庫の創業融資】自己資金なしでも融資を受けられる?の記事で解説していますので参照ください。
③事業に関連する経験をアピールできるようにする
こちらも非常に重要です。必ず職務経歴書等を追加で用意して事業に関する経歴をアピールするようにしましょう。自分の経験が弱いと感じる場合は、参画している共同経営者やパートナー等が十分な実績を持っている等、足りない経験について他の要素で補っていますという説明ができるように準備しましょう。
④事業計画書等の説明資料を追加で用意する
申し込み時の必要書類および面談担当者から別途依頼された資料について用意するのは当然ですが、必ずプラスαで面談に向けた追加の説明資料を用意するようにしましょう。③で記載した職務経歴書の他に、商品やサービスの説明資料、商流の説明、詳細な事業計画等、面談担当者が事業や申込者についてより理解できるように補足資料を作成しましょう。追加で用意する資料は全て申し込み時に提出した企業概要書または創業計画書と整合するものである必要がある点に注意しましょう。
⑤面談でよく聞かれる質問については回答を考えておく
上記の「(参考)創業融資の面談でよく聞かれる質問事項」に記載した例を含め、よく聞かれる事項についてはインターネットに多く事例が存在するため、一通り調べて自らの言葉で説明できるようにしましょう。
⑥税理士や専門家のサポートを得る
「自分だけでは準備が十分できているかわからない」という場合は、税理士等の専門家のサポートを入れることを検討してもよいと思います。
まとめ
日本政策金融公庫は政府系金融機関であり、民間よりも創業者の融資に積極的である一方、きちんと対策を行わないと審査落ちしてしまったり、あるいは希望する金額に届かないことになってしまいます。そのため、自分の信用情報を確認し、事業計画をしっかりと説明できるように準備を行うことが大切です。
認定経営革新等支援機関として当事務所でも創業融資についての支援を行っているため、不安な点がある方はぜひご相談いただければと思います。