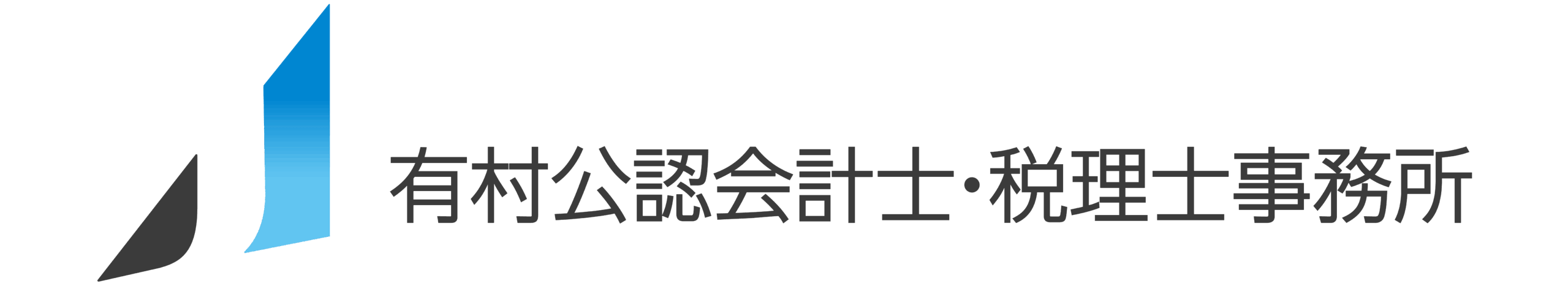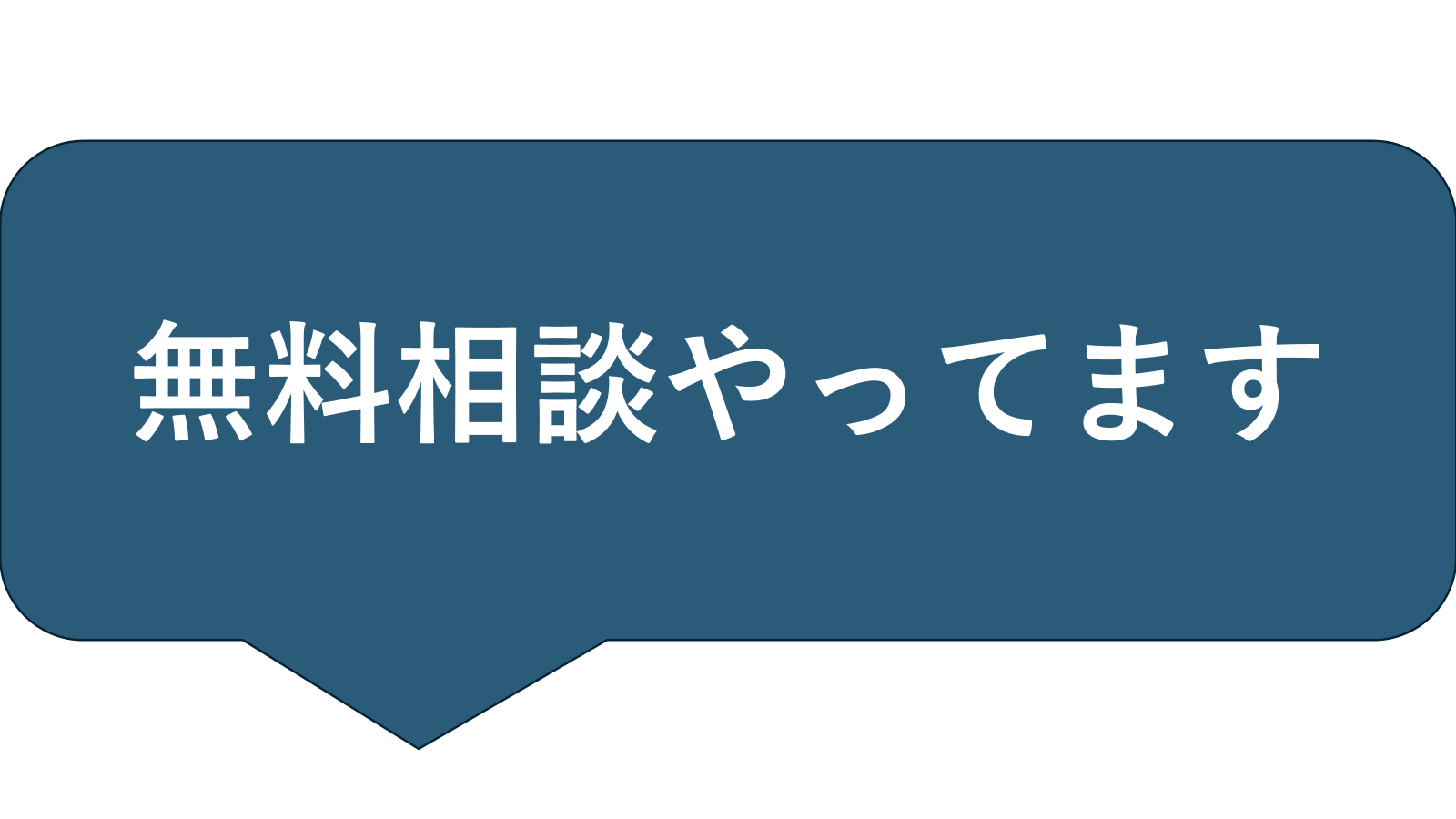準備のスケジュールと各期間における主な対応事項.webp)
IPO準備の主なTodo事項まとめ
IPO(新規株式公開)準備は、企業にとって大きな転換期であり、綿密な計画と実行が不可欠です。本記事では、IPO準備の全体スケジュールと各段階で実施すべき主要タスク、気を付けるべきポイントを詳しく解説します。
IPO(上場)までに最低限必要な期間
IPO準備には最低3年は必要
まず、IPO準備を行う期を上場申請期(N期)と呼び、上場申請直前期をN-1期、直前々期をN-2期と呼びます。
そして上場準備はN-3期から行うことが必要(以下の理由パート参照)であるため、最低3年程度かかると言われています。
理由:上場申請には直近2期分の財務諸表に関する監査報告書が必要だから
下記のToDoパートに記載していますが、N-3期中に監査法人と契約を結ぶ必要があります。これは、上場申請の際には直近2期分(N-1期とN-2期)の財務諸表について監査証明が必要とされているからです。
「N-2期の監査証明が必要なのであればN-2期の途中でもよいのでは」と思う方がいると思いますが、N-2期末の財務諸表について監査するためには、実務的にはN-2期の期初(=N-3期の期末)の貸借対照表の監査からスタートすることになるため、N-3期からの関わりが必要であるということになります。
これが、どうしても上場準備に最低3年かかる理由になります。
各期間における詳細な準備内容
各期間における主な対応事項まとめ
| 時期 | N-3期以前 | N-2期(直前前期) | N-1期(直前期) | 上場申請期 |
| 主なイベント | ・IPOを目指す意思決定 ・監査法人の選定 (・主幹事証券会社の選定) | ・内部管理体制の構築 ・監査法人の監査 (・主幹事証券会社の選定) | ・内部管理体制の運用 ・監査法人の監査 ・主幹事証券会社の審査 | ・証券取引所の審査 ・上場承認 ・株式上場 |
| やるべきTodo | ・事業計画の作成 ・資本政策の策定 ・ショートレビュー対応 ・組織体制整備 | ・諸規程の整備 ・各種業務フローの整備 ・内部監査(J-SOX)の整備 ・予実管理の実施 ・議事録・会議体の整備 | ・開示体制の構築 ・上場申請書類の作成 ・J-SOX対応 ・主幹事証券会社の審査対応 | ・証券取引所の審査対応 ・証券取引所へ上場申請 ・ロードショー対応 |
直前々々期(N-3期)以前
(1)事業計画及び資本政策の策定
まず、上場までの事業計画と資本政策を策定する必要があります。すでにVC等から資金調達を実行している場合はどちらも一定の馴染みがあると思いますが、外部投資家からの資金調達を行っていない場合は資本政策について馴染みが薄いかもしれません。資本政策とは、事業資金を調達するために立てる計画のことを言いますが、株式等を通じた調達金額や株主構成等のバランスを最適化する観点で立案されます。
上場までの各フェーズで必要な資金を明らかにし、株式等での調達が必要であれば各フェーズの株主構成やバリュエーションの見通しを立てることが重要です。
Point:このタイミングで上場時の想定時価総額(バリュエーション)を把握しておく
IPO準備を決断したタイミングで、上場時の想定時価総額を把握しておくことをおススメします。今の事業計画に基づいた上場時の時価総額が低すぎると、IPOまでの道のりは遠くなるため、3年後のIPOはおろか5年後でも難しいという状況になりかねません。日頃からVC等の外部投資家が入っていれば常にバリュエーションを気にしていると思いますが、外部出資を受けずに自社のみで成長してきた会社は必ずチェックすべきだと思います。
グロース市場全体の市況が低迷しているため、上場時の時価総額が低くなる傾向にある中、IPOを目指す会社が多いため、主幹事証券会社がIPO準備会社を選べる状況にあります。主幹事証券会社はIPO時の手数料収入で儲けるため、上場時の時価総額の目線が低いとなかなか主幹事の契約を結んでくれないことになります。
そのためまず、上場時の想定時価総額を把握し、低すぎる場合は中長期の事業計画を練り直すことが必要だと思います。一部の証券会社は100億円を基準に契約するかどうかを判断している状況にあるため、最低50億程度の時価総額は必要だと思います。
(2)監査法人の選定
先に記載した理由により、N-3期から監査法人と契約を結ぶ必要があります。以前は監査法人側のリソース不足等で、IPOを目指しているのに監査法人と契約できない状況が多発し、「監査難民」と呼ばれることもありましたが、IPO準備企業に対する支援を得意とする監査法人が続々と増えてきたため、監査難民問題は解消されつつあると思います。一方で大手の監査法人との契約はなかなか難しい状況も引き続きあると思います。
そして監査法人と契約を結ぶ前には通常ショートレビューと呼ばれる、IPOに向けた企業の課題を調査する活動を行うことが通常です。そのためN-3期の中ごろを目安にショートレビューを実行できるとよいでしょう。
(3)ショートレビューの実施
ショート・レビューでは、事前に資料依頼リストや質問リストが監査法人から送られた上で、数日間にわたって会社担当者へのインタビューや資料の閲覧を中心とした調査が行われ、最終的に上場に向けた課題の洗い出しを行います。ショート・レビューを実施することで会社の現状とIPOまでに行うべき対応事項が整理されることになります。通常かなりの量の指摘事項がくることになるため、しばらくの間は上場準備事項と言えばショートレビューの指摘事項対応という形になると思います。
(4)主幹事証券会社の選定
スケジュール管理や対応事項の管理、上場のための審査等、IPO準備において中心的役割を果たす証券会社のことを「主幹事証券会社」と呼びます。主幹事証券会社の選定はN-3期中に必ず対応しなければならない事項ではく、N-2期中(場合によってはN-1期に入ってから)に行う会社もありますが、IPO準備の中では必須の対応事項となっています。主幹事証券会社のメインの収入は上場時の株式発行手数料であるため、上場時の想定時価総額が高い企業と優先的に契約を結ぶという点は押さえておきましょう。
主幹事証券会社と契約が結べると、監査法人と同じく、社内管理体制に関する調査が行われ、IPOに向けた課題の一覧が共有されます。監査法人の時との違いは、監査法人は財務諸表をチェックするという立場であるため経理体制面により焦点を当てており、証券会社の指摘事項は全体的なガバナンス体制に焦点があたっているというイメージで問題ないです。
(5)プロジェクトチームの組成
IPO準備を円滑に進めるためには、社内にプロジェクトチームを編成することが必要です。プロジェクトチームは、IPO準備の全プロセスを統括し、各部門との連携を円滑に進める役割を担います。主にバックオフィス部門が主導することが多いと思いますが、経営陣、経理担当者、各部門のキーパーソン等、会社横断的な協力が不可欠です。
例えば、経営陣はIPOプロジェクトチームを支援する責任を負い、経理担当者は財務諸表の作成や会計監査への対応などを行い、法務担当者は契約書管理フローや稟議フローの構築等を行う等、役割分担を明確にすることで、各メンバーが責任を持ってタスクに取り組み、効率的な準備を進めることができます。
社内の人員で知見が足りない場合は、N-3期またはN-2期を目安にコンサルタントに依頼することを検討してもよいでしょう。
直前々期(N-2期)
監査法人や証券会社から共有された課題一覧に対する対応を含めた内部管理体制(ガバナンス体制)の構築が主になりますが、例えば下記のような項目があります。「N-2期中にガバナンス体制をしっかり整えて、N-1期で1年間しっかり運用できることを確認して、N期で上場申請する」という形で大きく理解するとよいでしょう。 そのため、N-2期は整える時期ということになります。
(1)規程類の整備
上場会社になるためにはありとあらゆる規程の整備が必要になります。主幹事証券会社が規程のサンプルを持っている場合が多いので、共有してもらって対応するのがよいでしょう。
(2)各種業務フローの整備
稟議規程や職務権限規程等を作る際に、取引ごとの稟議フローを定めることになります。稟議システム等を導入して、各取引について必要な承認が得られているかを確認するプロセスの構築が必要になります。
(3)予実管理の実施
中期経営計画を見直しながら予算を毎年策定し、月次で予算と実績の差異分析を行い取締役会で報告する必要があります。経営状況のタイムリーな共有が求められるため取締役会を月の中頃までには行う必要があり、そのため月次決算の早期化が伴うことが多いです。
(4)組織体制の整備
会社が目指すべき機関設計(※)を定め、これに基づいて監査役や社外取締役等の役員等の採用を進める必要があります。また、J-SOXやそのほかの内部監査業務を内部監査を担当する人をつける必要があります。また、執行役員制度の導入なども検討する必要があります。
※IPO準備会社においては、監査役会設置会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社の3パターンが候補としてあります。詳細は「【スタートアップ向け】IPO準備会社に必要な3つの機関設計と特徴まとめ」で解説していますのでご覧ください。
(5)J-SOX対応
内部統制報告制度(J-SOX)の対応として3点セットと言われる内部統制監査を実施するための資料の作成が必要です。内部統制とは、“経営者が会社を効率的かつ健全に運営するための仕組み”であり、さまざまな目的がある中で、財務報告の信頼性を担保(=きちんと財務諸表を作ること)する目的については、内部統制報告制度(J-SOX)として金融商品取引法によって定められており、上場企業は対応が義務付けられています。
すべての上場会社が実施が義務付けられているため、上場準備段階で上場後に備えて内部統制を整備・運用する必要があります。ただし上場後3年間は内部統制報告書(経営者による評価)に係る監査法人等の監査は免除されます。あくまで監査法人のチェックのみが免除されるだけで内部統制報告書の作成(経営者による評価)の対応は必要である点に留意ください。
直前期(N-1期)
N-1期はN-2期で整備したガバナンス体制をしっかりと運用する期間であるのが基本ですが、その他に下記のような対応事項があります。
(1)印刷会社の選定&開示体制の構築
上場後の財務数値の開示(短信や半期報告書等)をスムーズに行うことができるよう、N-1期のどこかで実際に開示資料を作成することが監査法人から求められることがあります。決算対応を早期で終わらせて開示書類を作成し、取締役会で承認するまでの一連のフローを社内でテストすることになります。
ここで、開示書類は上場後を想定して印刷会社(ディスクロージャー支援会社)の開示資料システム上で作った方がよいため、印刷会社の選定も行っておく必要があります。印刷会社は適時開示や株主総会招集通知等、証券関連の印刷や開示書類を作成するシステムを提供しており、日本では宝印刷とプロネクサスの2社が存在しているため、どちらかと契約する必要があります。
(2)上場申請書類(Ⅰの部&各説)の作成
Ⅰの部と各説と呼ばれる上場申請書類を作成する必要があります。Ⅰの部の正式名称は「新規上場申請のための有価証券報告書」であり直近2年間の財務諸表や監査報告書等が添付され、上場後には開示されます。また、各説は「新規上場申請者に係る各種説明資料」と呼ばれ、企業の沿革やビジネスモデル等も含めて企業について詳細に記載する資料です。こちらは世間に開示されない書類であり他社事例も基本的に確認できません。自社のみでの作成が困難なため、IPOコンサル等を入れて作成するのが通常だと思います。
(3)主幹事証券会社の審査対応
N期のはじめ頃に実行する場合もありますが、N-1期の終わりころに主幹事証券会社の審査がある可能性があります(いつ実施するかは上場タイミング次第です)。証券審査は数カ月にわたって行われ、証券会社の審査部からのQ&Aや資料依頼対応、実地調査などを経てガバナンスや事業の成長性に問題ないか等がチェックされます。
(4)株式事務代行機関(信託会社等)の選定
株式関係事務の円滑な実施のため上場(IPO)時の形式要件として株式事務代行機関の設置が求められており、この機関は株主名簿の管理等について代行してくれます。信託銀行等が代表的です。監査法人や証券会社と違い契約締結にハードルは特になく、IPO準備の過程で営業活動を受ける機会が出てくると思いますので自社にフィットする業者をタイミングを見て選定しましょう。
申請期(N期)
上場申請期は証券審査や東証審査がメインの対応事項となっています。
(1)上場申請と東証審査
主幹事証券会社の審査を通過すると、東京証券取引所に対して上場申請を行い、東証審査を受けることになります。こちらは約3カ月程度であり、証券審査と同様、質問をベースに上場する適性があるかを判断します。形式要件(財務数値や株式数等)や実質審査基準(継続性や経営の健全性など)を満たしているかという観点で審査されます。審査を超えることができれば晴れて上場承認という形になります。
(2)ロードショー対応
上場承認を受けた後はロードショーを行うことになります。ロードショーとはIPO実施前に行う機関投資家向けの説明会であり、企業の事業計画を説明することでIPOへの参加を促したり、上場時の想定発行株価に対する意見をヒアリングする目的があります。このヒアリング結果をもとに「XXX円~XXX円」という幅を持たせた形で株価の仮条件が決定され、その後ブックビルディングというプロセスの中で投資家に対して購入希望価格と投資株数の申告を募り公開価格が定まっていくことになります。
IPO(上場)準備で大切なポイント
対応事項の中で最もハードルが高いのは「事業の着実な成長(業績管理含む)」
IPO準備というとガバナンス体制を整える点にフォーカスが当たりがちですが、監査法人や証券会社の指摘事項に対してきちんと対応していけばガバナンス体制を作っていくことは問題なく可能です。必ずしも予定通りにいかないため非常に難しいのが事業計画通りに会社の業績を上げていくことです。業績が十分でないと形式要件を満たさないこととなったり、期待していた時価総額に届かないため上場時期をずらすということになってしまします。そのため事業の成長(業績管理)がIPO準備の中で最もハードルが高い点ということになります。
言いなりになりすぎず、自分で考えてみよう
個人的な意見ですが、監査法人や証券会社の指摘事項のあらゆる指摘事項に対して常にYesマンで従わなければならないというわけではありません。目的を達成する限りは、提案された解決策以外の方法がある場合もありますので、疑問がある場合は適宜質問を行い、違う解決策がないかを探すようにしましょう。敵対せず、IPOという共通のゴールに共に向かうパートナーとして適宜コミュニケーションしていくことが重要です。
IPO(上場)はあくまで通過点
上場はあくまで通過点であり、さらなる成長を目指すためのきっかけであることに留意しましょう。昨今、グロース市場においてはIPOを達成した後になかなか時価総額が伸びていかない状況が問題視されており、上場維持基準を厳格化するという話もでている状況です。「長期的な成長に必要なことは何か」という点を踏まえたうえでIPO準備を行っていくことが重要です。
まとめ
IPO準備は、企業にとって大きな挑戦ですが、ひとつひとつのステップを確実にこなしていくことで達成可能性を上げることができます。そして上場は企業にとって資金調達の機会を拡大するだけでなく、企業ブランドの向上や優秀な人材の獲得にもつながる大きなメリットをもたらすため、企業の成長戦略の一環として捉え、長期的な視点で取り組むことが重要です。準備にあたっては専門知識が求められる場面が非常に多いため、早めにIPOコンサルタントなどの専門家に相談し、アドバイスを受けながら準備を進めることをおススメします。当事務所でもサポートを行っているためお気軽にご相談下さい。