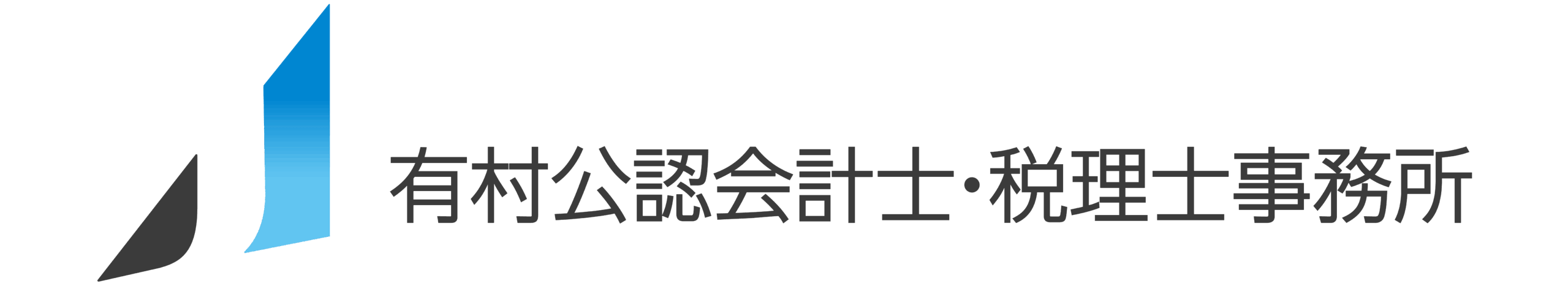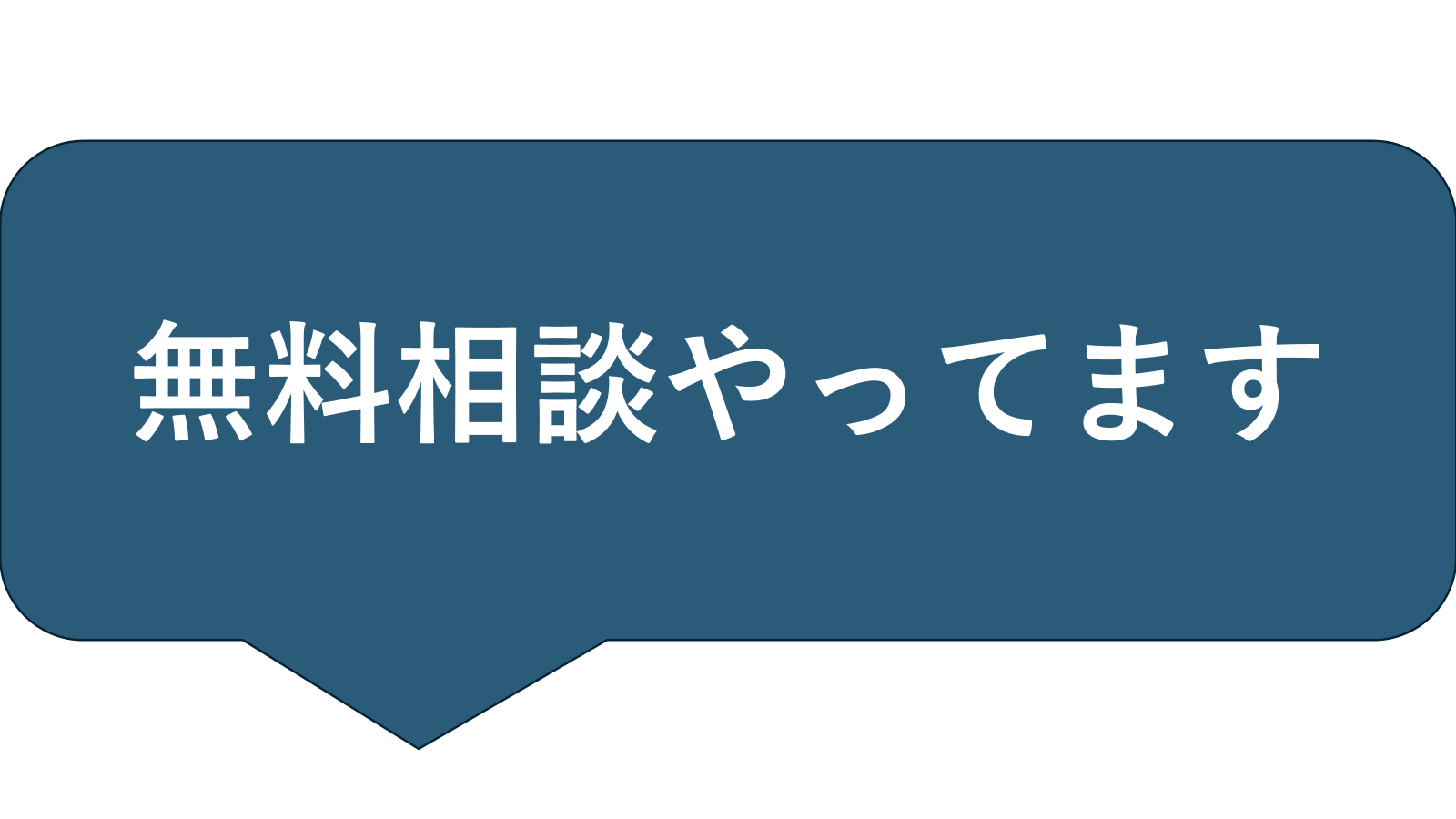IPO準備会社における機関設計まとめ
IPO(新規株式公開)準備における機関設計は、ガバナンス体制の構築において非常に重要な要素です。本記事では、IPO準備における機関設計の候補となる、監査役会設置会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社の3つの主要な機関設計について、それぞれの特徴を比較しています。会社ごとの状況に応じた適切な機関設計を選択し、スムーズなIPOを実現しましょう。
IPO準備会社における3つの機関設計
会社法上では機関設計のパターンは40以上あるとされていますが、公開会社かどうか、大会社かどうかという観点で場合分けすることができます。グロース市場へのIPOを前提とすると会社法上は「公開会社かつ大会社」になるため、詳細は省きますが結果として機関設計として考えられる候補は①監査役会設置会社、②監査等委員会設置会社、③指名委員会等設置会社の3つに限定されます。
なお、公開会社かどうかについては、すべての株式に譲渡制限を付けていると非公開会社となり、逆に株式の全部または一部について譲渡制限がないと公開会社となります。また、大会社かどうかという点については、資本金5億円以上または負債総額200億円以上であれば大会社に該当し、該当しない場合は非大会社となります。
以下にそれぞれの特徴を記載していきます。
①監査役会設置会社
監査役会設置会社においては、取締役会+監査役会+会計監査人の設置が必要です。
監査役会は3人以上で構成され、かつその半数以上を社外監査役としなければならない(会社法335条3項)とされています。
また、監査役の中から常勤の監査役を選定しなければならない(会社法390条1項、3項)とされているため、実務上は常勤1名+非常勤2名で構成されることが多いと思います。
監査役会の特徴は監査役のそれぞれに独任制が認められている点にあります。独任制とは、監査役会が存在しているもののひとりひとりの監査役が常勤か非常勤かを問わず単独で監査権限を行使できることを言い、このため監査役会設置会社は機動的な監査を行うことができるという特徴があります。また、監査役の任期は4年となっています(会社法336条1項)。一方で監査役は取締役会において議決権を有していない点にも注意です。
(参考)常勤監査役と非常勤監査役の違い
実は会社法上には常勤性についての定義はありません。私は監査役協会にも所属しており日頃から他社の監査役ともコミュニケーションしていますが、聞くところによると、以前は主幹事証券会社から「週3日以上の出社」が求められることもありましたが、コロナ禍後はフルリモートの会社も増えているため、会社の営業時間中に常時勤務しており、監査役監査手続きをきちんと計画通りに行える状況であるかという実質的な判断によることも多くなっているようです。監査役採用の際など実務上判断に困る場合は、主幹事証券会社の担当者と相談しておくとよいでしょう。一方で、非常勤監査役は常に監査業務に専念しているわけではないため、実務的には定期的な監査役会や取締役会への出席が主な業務となっています。
また、会社法上は常勤者が求められるのは監査役会設置会社のみですが、その他の機関設計においても常勤の監査等委員や監査委員がいることがほとんどであり、上場準備の過程で1人は求められると認識しておいてよいと思います。
②監査等委員会設置会社
監査等委員会設置会社においては、取締役会+監査等委員会+会計監査人の設置が必要です。
監査等委員会も3人以上で構成され、かつその半数以上を社外取締役とする必要があります(会社法331条6項)。ポイントは、それぞれの監査等委員は取締役であるという点です。そのため取締役会において議決権があります。
監査等委員である取締役の任期は2年となっていますが(会社法第332条1項)、その他の取締役の任期は1年です。
③指名委員会等設置会社
監査等委員会設置会社においては、取締役会+三委員会+会計監査人の設置が必要です。
三委員会とは、指名委員会・報酬委員会・監査委員会の3つの委員会を指します。指名委員会は取締役の選任・解任に関する議案内容を決定し、報酬委員会は取締役と執行役の個人別の報酬を決定し、監査委員会は取締役及び執行役の職務の執行を監査するという役割分担になっています。3つの委員会が経営を監督しながら、業務の執行については執行役が行うという形になっており、業務執行と経営の監督が分離されておりガバナンスが強いという特徴があります。
各委員会は3人以上の取締役で構成され、社外取締役が過半数を占める必要があります(会社法第400条3項)が、一人の取締役が複数の委員会の委員を兼任することは可能ですが、委員会が複数あるので人数が他の機関設計に比べて増える傾向にあります。
各取締役の任期は1年となっています(会社法第332条6項)。
また、過半数を占める社外取締役が取締役を選任したり報酬を決定したりすることとなるため、日本企業においては文化的になかなか受け入れられておらず、グロース市場においても採用している会社はほとんどいない状況です。
3つの機関設計に共通する要素
監査役会設置会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社それぞれにおいて、取締役会と会計監査人の設置は共通しているため概要を説明します。
①取締役会
取締役会は3人以上の取締役で構成され、業務執行に関わる重要事項の決議や取締役が職務を執行しているかの監督等を行う機関です。
監査役会設置会社の場合は社外取締役を1人以上選任する必要があります(会社法327条の2)。監査等委員会設置会社、指名委員会設置会社の場合は最低2名以上の社外取締役が必要です(会社法331条6項、会社法400条3項)。
ただしこちらは会社法上の話であり、コーポレートガバナンス・コードにおいて、上場会社は2名以上の独立社外取締役を置くことが求められているため、実務的には社外取締役の最低人数は2名だと押さえておきましょう(「独立」、「社外」の意味は後述)。なお、プライム市場においては取締役の3分の1以上を独立社外取締役にすることが推奨されています。
(参考)コーポレートガバナンス・コードとは
コーポレートガバナンス・コードとは、東京証券取引所が定めた企業統治に関するガイドラインで、経営の透明性や公正性を高めるための主要な原則を取りまとめたものです。あくまで東証のガイドラインであるため法的拘束力はありませんが、原則を守らない時には理由を開示することが求められている(これをコンプライ・オア・エクスプレイン(comply or explain)の原則と言います)ため、実務上はコーポレートガバナンス・コードの原則を守る必要があると考えておいてよいでしょう。
(参考)独立社外取締役の「独立性」とは
独立性とは、一般株主と利益相反が生じるおそれのない状態を言い、東京証券取引所が独立性に関するガイドラインを出しています。具体的には、下記のリストに当てはまる場合は独立性が阻害されているとされています。イメージとして、企業から多額の報酬を得ていたことなどにより企業に経済的に依存している状況である場合は独立性が阻害されると覚えておきましょう。
- a当該会社を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者又は当該会社の主要な取引先若しくはその業務執行者
- b当該会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
- c最近においてa又は前bに該当していた者
- cの2その就任の前10年以内のいずれかの時において次の(a)又は(b)に該当していた者
- (a)当該会社の親会社の業務執行者(業務執行者でない取締役を含み、社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、監査役を含む。)
- (b)当該会社の兄弟会社の業務執行者
- d次の(a)から(f)までのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の近親者
- (a)aから前cの2までに掲げる者
- (b)当該会社の会計参与(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。以下同じ。)
- (c)当該会社の子会社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役又は会計参与を含む。)
- (d)当該会社の親会社の業務執行者(業務執行者でない取締役を含み、社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、監査役を含む。)
- (e)当該会社の兄弟会社の業務執行者
- (f)最近において(b)、(c)又は当該会社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。)に該当していた者
(参考)社外取締役や社外監査役の「社外性」とは
社外取締役とは、下記の5つの要件を満たす取締役であるとされています(以下は会社法2条15号より)。要は基本的に過去にその会社で働いたことがあるかどうか、役員の親族かどうかで社外性が判断されます。これは社外監査役についても同様です(会社法2条16号参照)。
- 事業者(子会社を含む)の業務執行取締役でなく、かつ、就任前10年間に事業者等の業務執行取締役でなかったこと
- 就任前10年以内に事業者の取締役等であった場合には、その就任前10年間に事業者の業務執行取締役でなかったこと
- 事業者の親会社または親会社の取締役等・その他の使用人でないこと
- 事業者の親会社の子会社の業務執行取締役等でないこと
- 事業者の取締役等の配偶者または二親等内の親族でないこと
②会計監査人
会計監査人とは、企業の計算書類等を会計監査する機関で監査法人がなります。上場準備の過程で監査法人を選定すると思いますが、選定した監査法人が上場後は会計監査人の立場になります。上場前でも、監査等委員会設置会社や指名委員会設置会社を選んだ場合はその時点で正式に会計監査人を置く必要があり、会計監査人を置いた場合は会社法監査と呼ばれる会社法436条に基づいた監査が必要となるため、監査法人にかかるコストが上がることになります。
一方で、監査役会設置会社においても上場後は会計監査人の設置が必要ですが、上場準備中においてはいらないため、会社法監査は求められず、準金商法監査のみを実施することとなるため監査コストが少し抑えられることとなります。
3つの機関設計の特徴まとめと注意すべきポイント
3つの機関設計の比較表
これまでの説明に基づき、3つの機関設計について下記の表にまとめると以下のようになります。グロース市場においては監査役会設置会社と監査等委員会設置会社が大部分を占めている状況であるため、この2つの機関設計が検討対象になることが多いと思います。自社における役員の数と照らし合わせながら、今後あと何人くらいの役員を追加していく必要があるのかを検討するとよいでしょう。
| 監査役会設置会社 | 監査等委員会設置会社 | 指名委員会設置会社 | |
| 特徴 | ・監査役に独任制 ・監査役は取締役ではないので議決権なし | ・監査等委員は取締役であるため議決権あり | ・監査委員は取締役であるため議決権あり ・各委員会で過半数を占める社外取締役が取締役の選解任や報酬の決定等を行う |
| グロース市場における比率(※1) | 68.6% | 30.4% | 1% |
| 最低人数 | 取締役:3人 監査役:3人(常勤1名+2名非常勤) | 代表取締役:1名(※2) 監査等委員である取締役:3名 | 代表取締役:1名(※2) 各委員である取締役:3名 |
| 独立社外取締役 | 独立社外取締役:2名 ※CGコード上の要請 | 独立社外取締役:2名 ※CGコード上の要請 | 独立社外取締役:2名 ※CGコード上の要請 |
| 任期 | 取締役:2年 監査役:4年 | 監査等委員である取締役:2年 その他の取締役:1年 | すべての取締役:1年 |
| その他 | – | 会社法監査が必要となるため監査コスト増 | |
※1 コーポレート・ガバナンス白書 | コーポレート・ガバナンス | 日本取引所グループ の2023年データより
※2 代表取締役や監査等委員(監査委員)を兼任できない
注意ポイント①:機関設計を考えるタイミング
機関設計を考えるタイミングとして、早ければ早いに越したことはありませんが、多くの会社にとっては初めて監査役や監査等委員を選定する時に検討を行うと思います。通常、N-2期くらいが目安になると思います。非常勤監査役や独立社外取締役についてもN-1期中を目途に採用する会社が多いと思います。
注意ポイント②:よくある監査役会(監査等委員会)の構成と検討時の視点
よくある監査役会(監査等委員会)の3人の構成ですが、公認会計士・弁護士・その他の3名で構成されることが多いと思います。それぞれスタートアップ業界に精通していたり、IPO準備会社での勤務経験があったり、大企業で監査役監査業務等に携わっていたことがあるメンバーなどが選ばれることが多いと思います。
検討のポイントとして、監査役会設置会社である場合は取締役会における議決権がないですが、その他の機関設計の場合は取締役会において議決権を得ることになるので、ガバナンス面の強さだけでなく、経営判断を合理的に行うことができそうかという軸でも検討するとよいと思います。また、多様性推進の観点から女性役員比率を高める動きもあるため、3人のうちの1人を女性とすることを検討してもよいでしょう。
まとめ
上場準備会社の機関設計は①監査役会設置会社、②監査等委員会設置会社、③指名委員会等設置会社の3つのパターンがありますが、実務上は①監査役会設置会社と②監査等委員会設置会社が選択肢となることが多いと思います。ガバナンス面での特徴やそれぞれに求められる役員の数も異なるため、企業の状況に応じた機関設計を採用するとよいでしょう。当事務所ではIPO準備に関する支援も行っているため、お悩みがある方はぜひご連絡いただければと思います。