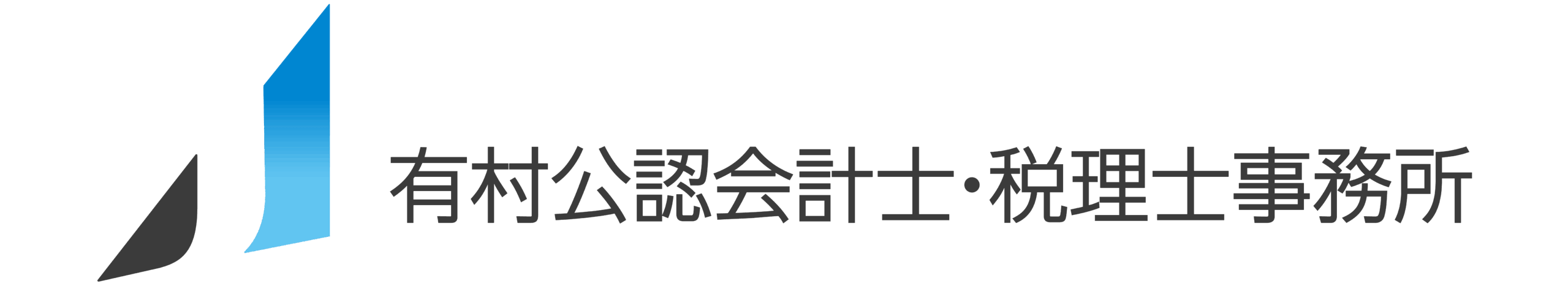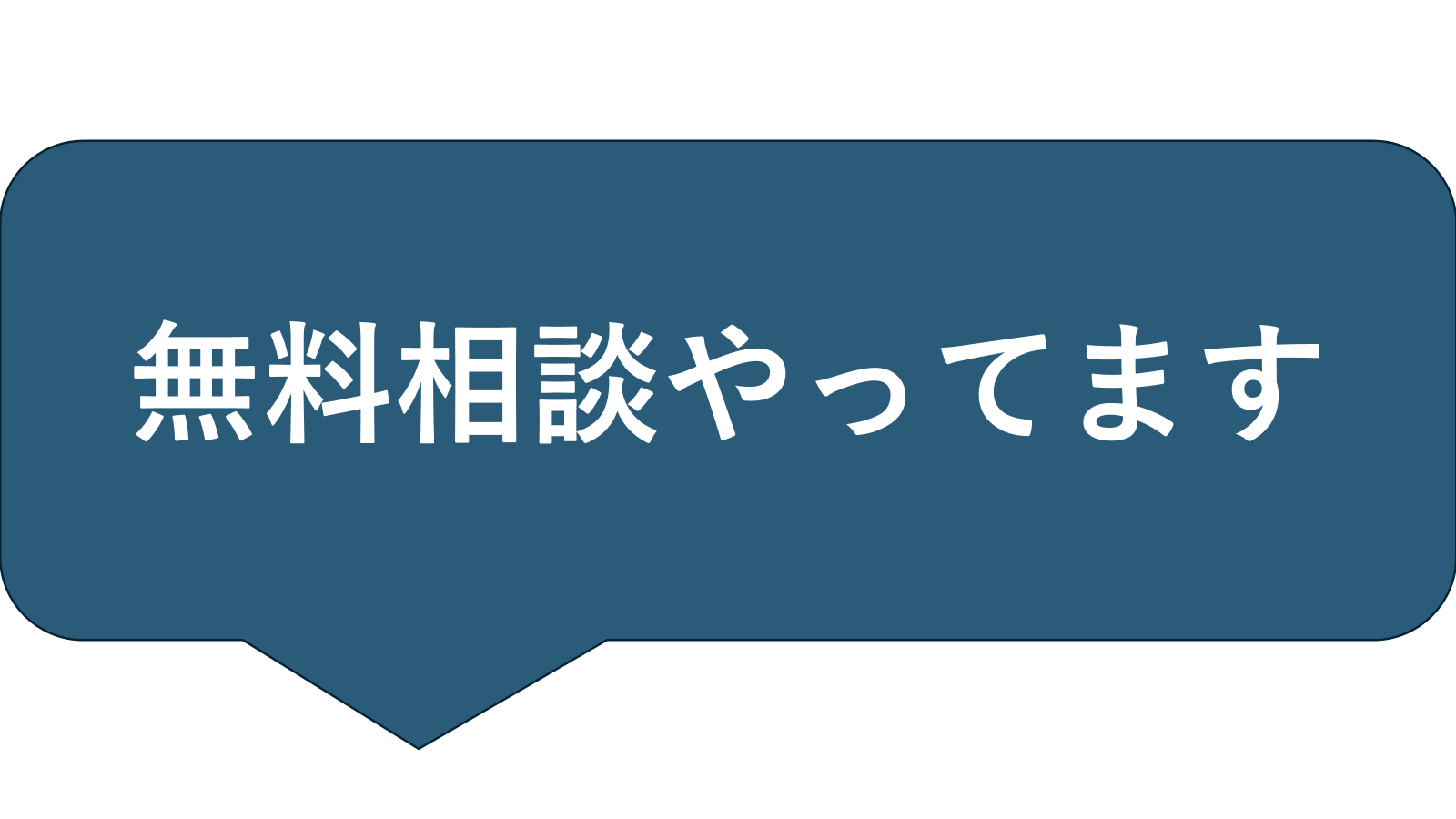経営セーフティ共済のメリット
経営セーフティ共済は中小企業にとって重要な財務支援制度であると同時に、賢く利用すれば節税効果も期待できます。本記事では、その概要から注意ポイントまで詳しく紹介します。
経営セーフティ共済の基礎知識
共済の概要と目的
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)は、中小企業の経営安定と事業継続を支援するために、中小企業事業者等が加入できる共済制度です。 中小企業事業者等が、事業活動中に発生する様々なリスクに備え、資金調達や事業の安定化を図ることを目的としています。 具体的には、取引先事業者が倒産するなどで売掛金の回収が困難になった場合に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐため、無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れができる仕組みとなっています。
利用対象
基本的には1年以上事業を継続している個人事業主と中小企業が対象となっています。資本金や従業員数などの細かい要件もありますので、詳細は加入手続きと合わせて中小機構のホームページで確認ください。
掛金の金額や限度など
掛金の金額や限度等は以下の通りです。
| 掛金月額 | 5,000円から20万円の範囲で5,000円単位で、加入申込み時に設定するほか、後日の金額変更も可能。 |
| 納付方法 | 掛金は、毎月、口座振替(引落し)。掛金の前納(前払い)も可能。 |
| 口座振替日 | 毎月27日(土・日・祝日の場合は翌営業日) |
| 積立限度額 | 800万円まで |
経営セーフティ共済のメリット
資金調達と倒産防止
経営セーフティ共済は、取引先の倒産などによって事業が困難になった場合に、すぐに借り入れができるため非常時の資金調達手段として活用することができます。
節税効果
経営セーフティ共済の掛金は損金算入が認められているため節税効果があります(この節税効果については後述します)。
解約手当金の存在
経営セーフティ共済には、解約手当金制度があります。 解約手当金は、共済契約を解約した場合に、支払われた掛金が一部または全額返還される制度です。自己都合の解約であっても、掛金を12か月以上納めていれば掛金総額の8割以上が受け取れ、40か月以上納めていれば納めた掛金全額を受け取ることができます。12か月未満での解約の場合は掛け捨てとなるため返還はありません。
低金利の貸付金利用
取引先事業者が倒産していなくても、共済契約者が臨時に事業資金を必要とする場合に、機構解約時の場合に支給される解約手当金の95%を上限として借入れできる一時貸付制度があります。
節税手法として利用する際の留意点
節税効果の例と留意点
例えば、年間売上高3,000万円、税引前利益が1,000万円の中小企業が、月額10万円の経営セーフティ共済に加入した場合、年間120万円の掛金が損金算入されます。
この場合、税引前利益は880万円となり、税率を仮に30%とすると、税金は税引前利益が1,000万円の場合よりも36万(=120万円×30%)低く抑えることができます。掛け金が800万円になるまで経費にすることができるため、約7年で240万円(=800万円×30%)の節税効果があります。
一方で、解約時の解約手当金は全額課税されるため、解約手当受領時は240万円(800万×30%)の税金を支払う必要があります。これを避けるためには解約時の益金を退職金とぶつける等で一定の工夫する(=出口戦略を立てる)必要がある点に注意しましょう。
経営セーフティ共済は掛け金の拠出を伴い、かつ、解約時の手当金は課税対象となるため、解約時の出口戦略が定まっていない場合は、基本的にキャッシュアウトを伴う課税の繰り延べに該当します。そのため、節税のみを目的とする場合は、現金残高に余裕があり、事業投資の予定もない場合のみ行うべきです(節税効果のタイプごとの考え方についてはこちらの記事をご確認ください)。
しかし実は貸付制度を利用することで資金繰りの課題も解決することができます。一時貸付制度という名称ですが、実は利息を支払って毎年借換を行えば、ずっと返済せずに繰越すことができます。つまり、実質的に資金繰りへの影響がなくなり、”キャッシュアウトのない”課税の繰り延べに変換することができます。
利息の支払いはありますが、そもそも低金利であるため節税メリットの方が大きくなります。また、当該貸付制度は銀行からの借り入れなどと違い、審査がないため手続き上も非常に簡単で、素早く借り入れを実行することができ、事務的な手間もほとんどありません。
前納について
前納をすることによって最大で460万円まで損金算入することが可能です(例:12月決算の場合:1月から11月まで月20万円を支払って、12月に1年分(240 万円)を前納)。ただこちらも基本的には資金繰りに影響を与えるものであるため、慎重に検討しましょう。「前納したけどお金が足りなくなって借入せざるを得なくなった」等は本末転倒だと思います。資金繰りの影響を抑える必要がある場合は一時貸付制度の利用を検討しましょう。
2024年10月改正の影響
節税を目的として短期間で脱退・再加入を不自然に繰り返す事例が増えていたことに対する税制改正として、2024年10月以降に共済契約を解約して再加入する場合、その解約の日から2年を経過する日までの間に支出する掛金については、必要経費または損金の額に算入できないこととなりました。
2年間損金にならない期間が定められただけですので、引き続き解約して2年後に再加入するという手もありますが、解約後の再加入しない期間や積立残高が少ないうちは、万が一取引先が倒産した場合に、必要な融資が受けられません。自社の事業状況に照らして、経営セーフティ共済の本来のメリット(非常事態の融資という保険的な意味合い)と節税効果のどちらに重きを置くのかという点を考慮し、今後のアクションを検討するとよいでしょう。
まとめ
経営セーフティ共済は、事業の安定化だけでなく節税対策としても有効な手段です。一方で節税目的として行う場合は、解約時の出口戦略をしっかりと定めないと、単に資金繰りを悪化させるだけの可能性もあります。資金繰りへの影響を減らすためには一時貸付金制度の利用も積極的に検討すべきでしょう。